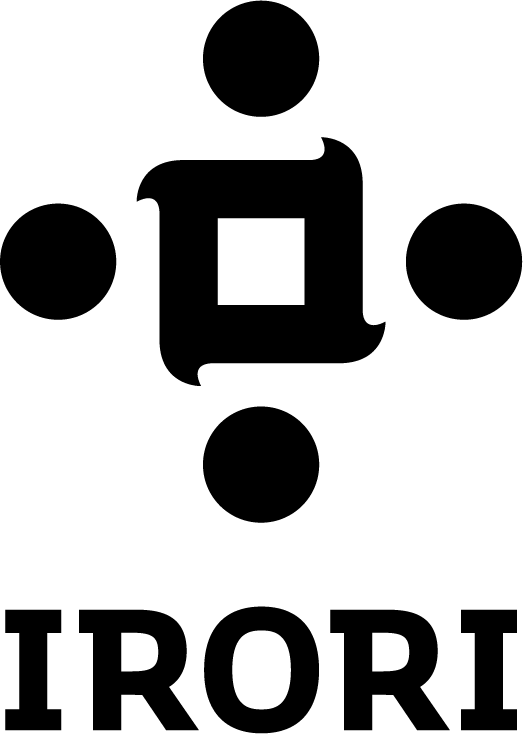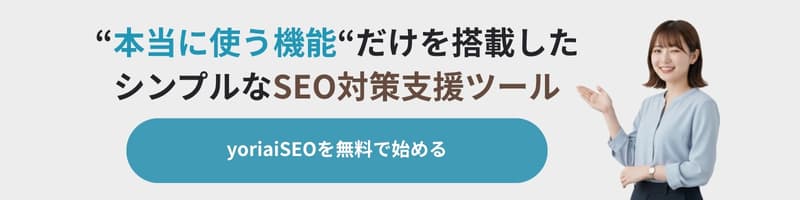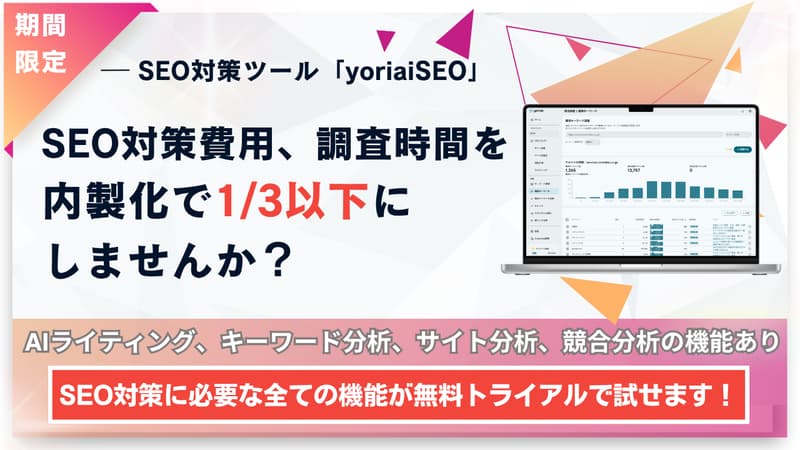「ステークホルダー」という言葉を、聞いたことがない、という人はもうほとんどいないでしょう。しかし、「その意味は?」「なぜ重要なの?」と問われると、明確に答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。本記事では、「ステークホルダーとは?」という根本的な疑問から、その種類、分析方法、関係構築の具体的手法、さらにはCSR、ESG、CSVといった関連概念との違いまで、初学者の方にも理解しやすい言葉や例をつかって、分かりやすく徹底解説します。
【記事を読むメリット】
この記事を読むことで、あなたは以下のことができるようになります。
- ステークホルダーの意味と重要性を理解できる
- あなたの企業に関わるステークホルダーを具体的に特定できる
- ステークホルダーとの良好な関係を築く方法が分かる
- 企業価値を高めるためのヒントが得られる
ステークホルダーとは?企業を取り巻く重要な関係者たち
ステークホルダーとは、企業活動に影響を受け、また影響を与える人々のこと
ステークホルダーとは、企業や組織の活動に影響を与え、または影響を受ける個人や集団を指します。簡単に言うと、会社と何かしらの関係がある人たちのことです。英語の “Stakeholder” は、”Stake”(杭、賭け金、利害)と “Holder”(保有者)を組み合わせた言葉です。つまり、組織の活動に関係し、何らかの利害、つまり、プラス・マイナスの影響を受ける人たち、ということです。
具体例:あなたもステークホルダー
例えば、あなたが学校に通っているなら、あなた自身が学校の「ステークホルダー」です。学校の授業の質や、校則、イベントなどによって、あなたは影響を受けます。また、あなたが学校の評判を良くするような活動をすれば、学校に良い影響を与えることになります。
普遍性:企業だけでなく、あらゆる組織に存在する
この「ステークホルダー」という考え方は、企業だけでなく、NPO(非営利団体)、学校、病院、政府機関など、あらゆる組織に当てはまります。
重要性:ステークホルダーは、企業の存続と成長に不可欠な存在
ステークホルダーは、企業にとって「なくてはならない存在」、いわば「生命線」です。 企業が長く続き、成長していくためには、ステークホルダーとの良好な関係が不可欠です。
なぜ重要なのか?:具体的な理由
| 理由 | 詳細 |
| 企業の存続に不可欠 | 顧客、従業員、投資家などがいなければ、企業は成り立たない |
| リスクの回避 | ステークホルダーを無視すると、不買運動や風評被害などのリスクが高まる |
| 企業価値の向上 | ステークホルダーとの良好な関係は、企業の評判や信頼性を高め、長期的な企業価値向上に繋がる |
| イノベーションの促進 | 顧客や従業員など、様々なステークホルダーからの意見は、新しい商品やサービスを生み出すためのヒントになる |
顧客が商品を買ってくれなければ、従業員が働いてくれなければ、投資家がお金を出してくれなければ、企業は成り立ちません。
例えば、顧客が「この企業の商品は買いたくない」と思ったり、従業員が「この会社では働きたくない」と思ったりしたら、企業にとって大きな痛手となります。
ステークホルダーとの関係が良好であれば、企業の評判は良くなり、より多くの顧客や投資家を引き付けることができます。これは企業の長期的な成長や価値の向上へとつながっていきます。
顧客や従業員など、様々な立場の人々からの意見は、新しい商品やサービスを生み出すための貴重なヒントになります。
現代社会とステークホルダー:SDGs達成のために、全ての組織がステークホルダーと協働する必要がある
近年、世界中で「SDGs(エスディージーズ)」という言葉が注目されています。これは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、貧困、飢餓、気候変動など、地球規模の問題を解決するために、国連が定めた17の目標です。
これらの目標を達成するためには、企業だけでなく、あらゆる組織がステークホルダーと協力し、社会問題の解決に取り組むことが求められています。
味の素グループは、「ASV」(Ajinomoto Group Creating Shared Value)という独自の取り組みを通じて、栄養改善などの社会課題解決と企業成長の両立を目指しています。これは、企業が社会に良い影響を与えながら、自社の利益も上げていくという考え方です。(参考:味の素グループ)
ステークホルダーの種類:企業を取り巻く多様な関係者
ステークホルダーは、大きく内部ステークホルダーと外部ステークホルダーに分けられます。さらに、外部ステークホルダーは、一次ステークホルダーと二次ステークホルダーに分類できます。
内部ステークホルダー:組織内部の人々
内部ステークホルダーとは、組織の内部にいる人々のことです。
内部ステークホルダーの例
| ステークホルダー | 説明 | 具体例 |
| 経営者 | 会社の方向性を決め、重要な意思決定を行う | 社長、CEO、役員 |
| 従業員 | 会社の事業活動を支える労働力を提供する | 正社員、契約社員、パート・アルバイト |
| 取締役会 | 経営者の仕事を監督し、株主の利益を守る | 取締役、監査役 |
| 労働組合 | 従業員の代表として、会社と交渉し、労働条件の改善などを目指す(存在する場合) | 〇〇企業労働組合など。企業や業種ごとに存在。日本労働組合総連合会(連合)など |
企業の社長や役員など、経営を担う人々は、最も重要な内部ステークホルダーです。彼らは、企業の進むべき方向性を決め、事業計画を立て、日々の業務を監督します。
従業員は、企業の製品やサービスを生み出し、顧客に提供する、まさに企業活動の担い手です。従業員がいなければ、企業は成り立ちません。
取締役会は、経営者が正しく経営を行っているかを監督する役割を担っています。株主の利益を守ることも重要な役割の一つです。
労働組合は、従業員の意見をまとめ、給料や労働時間などの労働条件について、会社と交渉する組織です。全ての会社にあるわけではありませんが、従業員の権利を守るために重要な役割を果たしています。
外部ステークホルダー:組織の外部から影響を与える人々
外部ステークホルダーとは、組織の外部にいるけれども、組織と関係がある人々のことです。
一次ステークホルダーとは、企業と直接的にお金のやり取りがある人々のことです。
一次ステークホルダーの例
| ステークホルダー | 説明 | 具体例 |
| 顧客 | 企業の商品やサービスを購入する | 一般消費者、企業顧客 |
| 株主・投資家 | 企業にお金を投資し、経営に参加する権利を持つ | 個人投資家、銀行、証券会社などの機関投資家 |
| サプライヤー | 企業に商品やサービスの元となる材料や部品を供給する | 部品メーカー、卸売業者、原料の生産者(農家など) |
| 債権者 | 企業にお金を貸し付けている | 銀行、社債権者(社債という企業の借用証書を買って、企業にお金を貸している人) |
顧客は、企業の商品やサービスを購入してくれる、最も重要なステークホルダーの一つです。顧客がいなければ、企業は利益を上げることができません。
たとえば、あなたがコンビニでおにぎりを買う時、あなたはそのコンビニの「顧客」であり、ステークホルダーになります。
株主や投資家は、企業にお金を投資することで、企業の成長を支援します。企業は、株主や投資家から集めたお金を使って、新しい事業を始めたり、設備を充実させたりすることができます。
たとえば、あなたが将来、ある企業の株を買ったら、あなたはその企業の「株主」であり、ステークホルダーになります。
サプライヤーは、企業が商品やサービスを作るために必要な材料や部品を供給する、重要なパートナーです。
たとえば、自動車メーカーにとって、タイヤやエンジンなどの部品を供給してくれる会社は、「サプライヤー」であり、ステークホルダーになります。
債権者は、企業にお金を貸し、企業の資金繰りを支援します。企業は、債権者から借りたお金を使って、事業を運営したり、設備投資をしたりします。
たとえば、ある企業が銀行からお金を借りたら、その銀行は「債権者」であり、ステークホルダーになります。
二次ステークホルダーとは、企業と直接的にお金のやり取りはないものの、間接的に影響を受けたり、与えたりする人々のことです。
二次ステークホルダーの例
| ステークホルダー | 説明 | 具体例 |
| 政府機関・自治体 | 法律や条例を作り、企業活動を規制したり、支援したりする | 経済産業省、環境省、市役所、町役場 |
| 地域社会 | 企業が事業活動を行う地域の住民 | 近隣住民、自治会 |
| NGO/NPO | 環境保護や人権擁護など、特定の社会問題の解決に取り組む非営利団体 | グリーンピース、アムネスティ・インターナショナル、日本赤十字社 |
| メディア | 企業活動に関する情報を発信し、世論に影響を与える | 新聞、テレビ、インターネットメディア |
| 競合他社 | 同じ市場で商品やサービスを提供し、競争関係にある企業 | 同じ業界の別の会社 |
政府機関や自治体は、企業活動に関する法律や条例を作り、企業がルールを守って事業を行うように監督しています。また、企業活動を支援する役割も担っています。
たとえば、環境省は、企業が環境汚染をしないように規制したり、環境に優しい技術の開発を支援したりしています。
企業が事業活動を行う地域の住民は、企業の活動によって様々な影響を受けます。例えば、工場から出る騒音や排気ガスなどの問題もあれば、企業が雇用を生み出し、地域経済を活性化させるという良い影響もあります。
たとえば、あなたの家の近くに新しく工場ができたら、あなたはその企業の活動の影響を受ける「地域社会」の一員であり、ステークホルダーになります。
NGOやNPOは、環境問題や人権問題など、様々な社会問題の解決に取り組んでいます。企業に対して、社会的責任を果たすように働きかけることも重要な役割です。
たとえば、地球温暖化の問題に取り組むNGOは、企業に対して、二酸化炭素の排出量を削減するように求めることがあります。
新聞、テレビ、インターネットなどのメディアは、企業の活動に関する情報を発信し、世論に大きな影響を与えます。
たとえば、ある企業の不祥事がメディアで大きく報道されると、その企業の評判は大きく低下する可能性があります。
同じ市場で商品やサービスを提供する競合他社は、お互いに影響を与え合っています。競争することで、より良い商品やサービスが生まれるというメリットもあります。
たとえば、スマートフォン市場では、アップルやサムスンなどの企業が、より良い製品を開発するために競争しています。
ステークホルダーの多角的視点:「権力」「正当性」「緊急性」で対応の優先順位を見極める
全てのステークホルダーに同じように対応することは、現実的には難しいことです。そこで、「権力」「正当性」「緊急性」という3つの視点からステークホルダーを分析し、対応の優先順位を考えることが重要です。
3つの視点
| 視点 | 説明 | 例 |
| 権力 | 企業の意思決定に影響を与える力の大きさ。 | 主要株主、政府機関、大手取引先などは、企業に対して大きな影響力を持つ |
| 正当性 | そのステークホルダーの主張が、社会的に認められるものであるかどうか。 | 労働組合、消費者団体、環境NGOなどは、それぞれの立場から正当な主張を行う |
| 緊急性 | そのステークホルダーの主張や要求が、迅速な対応を必要とするものであるかどうか。 | 製品事故の被害者、大規模な環境汚染の影響を受けた地域住民、内部告発などは、企業に対して迅速な対応を求める可能性が高い |
「権力」とは、企業に対して、何かを強制したり、やめさせたりすることができる力のことです。例えば、大株主は、企業の経営方針に大きな影響を与えることができます。
「正当性」とは、その主張が社会的に正しいと認められるかどうか、ということです。例えば、労働組合が「従業員の労働条件を改善してほしい」と主張することは、正当な主張だと言えます。
「緊急性」とは、すぐに対応しなければならないかどうか、ということです。例えば、製品事故が発生した場合、被害者への対応は非常に緊急性が高いと言えます。また、企業の不正行為を告発する「内部告発」も、迅速な対応が求められるでしょう。
一般的に、「権力」「正当性」「緊急性」の全てが高いステークホルダーは、最優先で対応すべきです。一方、いずれの視点も低いステークホルダーは、優先順位が低くなります。
ステークホルダー分析:関係者を理解し、適切な対応を導き出す
ステークホルダー分析とは、企業に関わる様々なステークホルダーを特定し、それぞれのステークホルダーとの関係性を分析することで、適切な対応策を導き出すための手法です。
ステークホルダー分析の重要性:企業とステークホルダーの良好な関係構築のために不可欠
ステークホルダー分析を行うことで、企業は以下のメリットを得ることができます。
- ステークホルダーのニーズや期待を把握できる
- ステークホルダーとの関係におけるリスクを特定できる
- 効果的なコミュニケーション戦略を立案できる
- ステークホルダーとの良好な関係を構築できる
ステークホルダーの影響度評価:重要度を見える化し、優先順位をつける
影響度評価とは、各ステークホルダーが企業に与える影響の大きさを評価し、対応の優先順位を決めるためのものです。
一般的には、以下の4つの項目で評価します。
- 影響力: 企業活動に影響を与える力の大きさ
- 関心度: 企業活動への関心の高さ
- 依存度: 企業への依存の程度(企業が相手にどの程度依存しているか、逆もしかり)
- 協力/敵対の可能性: 企業に協力する可能性、または敵対する可能性
各項目を、例えば「高」「中」「低」の3段階で評価します。
影響度評価の例
| ステークホルダー | 影響力 | 関心度 | 依存度 | 協力/敵対の可能性 | 総合評価 |
| 顧客 | 高 | 高 | 中 | 協力 | 高 |
| 株主 | 高 | 中 | 高 | 場合による | 高 |
| 従業員 | 中 | 高 | 高 | 協力 | 中 |
| 地域社会 | 中 | 中 | 低 | 場合による | 中 |
| 政府機関 | 高 | 低 | 低 | 規制 | 中 |
総合評価が高いステークホルダーは、優先的に対応すべきステークホルダーです。例えば、顧客の影響力と関心度は高いため、最優先で対応する必要があります。
ステークホルダーエンゲージメント:関係構築の現状を把握し、改善する
ステークホルダーエンゲージメントとは、企業がステークホルダーと積極的に関わり、良好な関係を築こうとする活動のことです。
ステークホルダーとの良好な関係は、企業の持続的な成長に不可欠です。エンゲージメントを通じて、ステークホルダーの意見や要望を理解し、それらを企業活動に反映させることで、ステークホルダーからの信頼を高めることができます。
たとえば、顧客としっかり対話して、顧客が求めているもの、不満に思っていることを聞き出せば、それを新製品の開発に活かすことができます。そうすれば、顧客の満足度も上がり、企業への信頼感も高まるでしょう。
エンゲージメントレベルとは、企業とステークホルダーとの関係の深さを表すものです。
エンゲージメントレベルの例
| レベル | 説明 | 具体例 |
| 情報提供 | 企業からステークホルダーへの一方通行の情報提供 | IR資料の公開、ニュースリリースの配信、ウェブサイトでの情報発信 |
| 意見聴取 | ステークホルダーからの意見を収集する | アンケート調査、カスタマーセンターへの問い合わせ、ソーシャルメディアのモニタリング |
| 対話 | 双方向のコミュニケーションを通じて、相互理解を深める | 株主総会、地域住民との意見交換会、顧客との座談会 |
| 協働 | ステークホルダーと協力して、共通の目標達成を目指す | NPOと連携した社会貢献活動、顧客との新製品開発、産学連携プロジェクト |
一般的に、エンゲージメントレベルが高いほど、ステークホルダーとの関係は良好であると言えます。企業は、各ステークホルダーとのエンゲージメントレベルを分析し、必要に応じてレベルを高めるための施策を実行する必要があります。
全てのステークホルダーに同じように対応することは、現実的には難しいことです。そこで、影響度評価の結果とエンゲージメントレベルの分析結果を組み合わせて、対応の優先順位を決め、経営資源を効果的に配分することが重要です。
優先順位付けの例
| ステークホルダー | 影響度 | エンゲージメントレベル | 優先度 |
| 顧客 | 高 | 対話 | 高 |
| 株主 | 高 | 情報提供 | 中 |
| 従業員 | 中 | 協働 | 高 |
| 地域社会 | 中 | 意見聴取 | 中 |
| 政府機関 | 高 | 情報提供 | 中 |
例えば、影響度が高い「顧客」に対しては、「対話」レベルの深いエンゲージメントを行うことが重要です。一方、影響度が中程度の「株主」に対しては、「情報提供」レベルのエンゲージメントで十分な場合もあります。
ステークホルダーマネジメント:企業と社会が共に発展するための関係構築
ステークホルダーマネジメントとは、ステークホルダーとの関係を適切に管理し、企業と社会が共に発展することを目指す活動です。
ステークホルダーマネジメントの手法:具体的な4つのステップ
一般的に、以下の4つのステップで進められます。
- コミュニケーション戦略の策定
- リスクマネジメント
- パフォーマンス評価
- ステークホルダーとの共創
コミュニケーション戦略の策定:ステークホルダー別の「対話」の設計図
ステークホルダーごとに、どのような方法で、どのくらいの頻度でコミュニケーションを行うかを定めた計画を作成します。
- 顧客: 製品の使い方動画をウェブサイトで公開したり、購入者アンケートで意見を集めたりする。また、お客様相談室で、問合せに迅速に対応する。
- 従業員: 社内報で会社の業績や今後の計画を説明したり、社長と直接話せる座談会を実施したりする。また、社内アンケートで、働き方に関する意見を集める。
- 株主・投資家: 決算説明会で会社の業績を説明したり、個人投資家向けの説明会を実施したりする。また、ウェブサイトで、財務情報などを公開する。
- 地域社会: 工場周辺の清掃活動を一緒に行ったり、地域のお祭りに参加したりする。また、地域住民向けの広報誌で、会社の活動内容を説明する。
リスクマネジメント:ステークホルダーとの関係に潜む「危険」の芽を摘む
ステークホルダーとの関係において、どのような問題が起こる可能性があるのかを予測し、問題が起こらないように対策を講じたり、問題が起こったときにどのように対応するかを決めたりすることです。
- 製品の安全性: もし製品に問題があったらすぐに知らせ、回収するための手順を決めておく。また、定期的に製品の品質を検査する。
- 環境問題: 工場から出る煙や汚れた水を、環境に影響が出ないレベルに抑えるための設備を導入する。また、環境への影響を定期的に測定する。
- 労働問題: 従業員が働きやすい環境を整え、ハラスメントを防止するためのルールを徹底する。
- 情報漏洩: 個人情報などの重要なデータが外部に漏れないよう、セキュリティ対策を強化する。また、従業員に情報管理に関する教育を行う。
パフォーマンス評価:ステークホルダーとの関係を「見える化」し、改善する
ステークホルダーマネジメントの成果を定期的に評価し、改善していくことが重要です。
ステークホルダーマネジメントがうまくいっているかどうかを評価し、改善するための指標のことです。
- 顧客満足度: 顧客にアンケートを取り、商品やサービスにどのくらい満足しているかを数字で表す。(例:5段階評価で平均4.5以上を目指す)
- 従業員エンゲージメント: 従業員にアンケートを取り、仕事へのやる気や会社への愛着がどのくらいあるかを数字で表す。(例:従業員満足度調査で、良い評価を得た人の割合を80%以上にする)
- メディア分析: 新聞やテレビ、インターネットなどで、自社がどのように報道されているかを分析する。(例:良い内容の記事と悪い内容の記事の数を比較する)
- 社会的責任投資(SRI)指標: 企業の社会的責任への取り組みを評価する指標。(例:DJSI(企業の社会的責任に関する指標)のスコアを毎年向上させる)
ステークホルダーとの共創:「一緒に創る」ことで生まれる新たな価値
近年、企業がステークホルダーと協力して、新しい商品やサービスを開発したり、社会問題を解決したりする「共創」の取り組みが注目されています。
- 顧客との共創: レゴは、「LEGO IDEAS」というウェブサイトで、顧客から新しい製品のアイデアを募集しています。顧客の意見を積極的に取り入れることで、顧客満足度の向上とイノベーションの促進を図っているのです。
- NPOとの共創: 花王は、国際NGO「ウォーターエイド」と協力して、開発途上国での衛生環境の改善に取り組んでいます。社会貢献と企業イメージの向上を同時に実現しているのです。
- 地域社会との共創: ヤマト運輸は、自治体と協力して、高齢者の見守りサービスや買い物代行サービスを提供しています。地域社会の課題解決に貢献すると同時に、新たなビジネスチャンスを創出しているのです。
ステークホルダーと関連する概念:CSR、ESG、CSVの違いを理解する
CSR(企業の社会的責任):企業は、社会の一員としての「責任」を果たす
CSRとは、「Corporate Social Responsibility」の略で、日本語では「企業の社会的責任」と訳されます。企業は、利益を追求するだけでなく、環境問題や人権問題など、社会的な課題の解決にも貢献すべきである、という考え方です。
「企業は、社会の一員として、法令を守り、倫理的な行動を取らなければならない」ということを定めたものです。この中で、「ステークホルダーとの対話の重要性」が強調されています。(参考:日本経済団体連合会)
CSRは、企業がステークホルダーに対して果たすべき責任をまとめたもの、と考えることができます。
ESG(環境・社会・ガバナンス):企業を評価する「新たなモノサシ」
ESGとは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を取った言葉です。近年、企業を評価する上で、財務情報だけでなく、ESGへの取り組みも重視されるようになってきました。
ESGの中の「Social(社会)」は、従業員、顧客、地域社会など、ステークホルダーとの関係性に関する項目が含まれます。
近年、ESGに積極的に取り組む企業に投資する「ESG投資」が世界的に拡大しています。企業は、ESGの観点からも、ステークホルダーとの関係を重視する必要があるのです。
「コーポレートガバナンス・コード」とは、企業がどのように経営されるべきかを示したルールです。金融庁は、この中で、企業に対してESG情報の開示を推奨しています。金融庁
CSV(共通価値の創造):社会課題の解決と企業利益を「両立」する
CSVとは、「Creating Shared Value」の略で、日本語では「共通価値の創造」と訳されます。これは、企業が社会課題の解決に取り組むことで、社会的な価値を生み出すと同時に、企業の利益にもつながる、という考え方です。
CSVは、ステークホルダーとの協働を通じて、社会と企業の両方にとって価値のあるものを創造することを目指すものです。
まとめ:ステークホルダーと共に歩む、持続可能な未来
本記事では、「ステークホルダーとは?」という疑問に答え、その種類、分析方法、関係構築の手法、関連する概念まで、幅広く解説しました。
結論として、ステークホルダーは、企業が持続的に成長し、社会から信頼されるために、最も重要な「パートナー」です。
企業と社会の持続的な発展のために
企業は、目先の利益だけでなく、長期的な視点を持ち、ステークホルダーとの対話を重ね、共に課題を解決していくことが求められています。それこそが、企業と社会の持続的な発展、そして私達のより良い未来へとつながっていくのです。
この記事が、「ステークホルダー」への理解を深め、あなたの企業経営、そしてあなた自身のキャリアに役立つことを心から願っています。