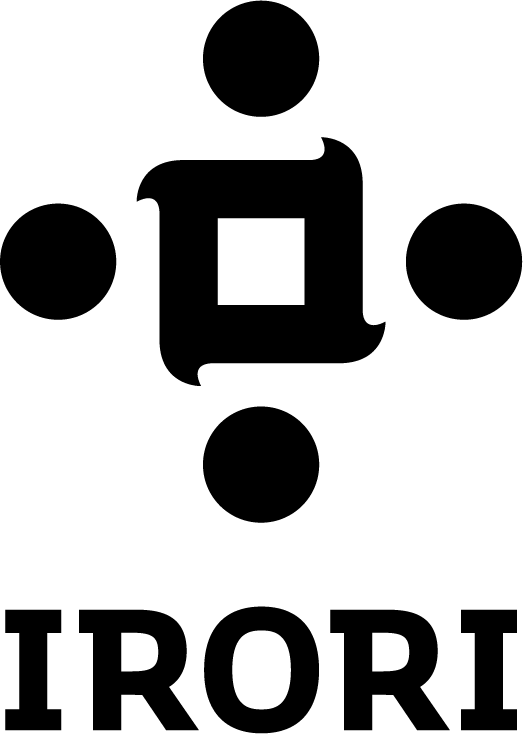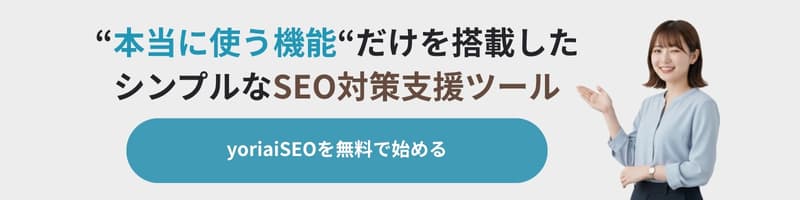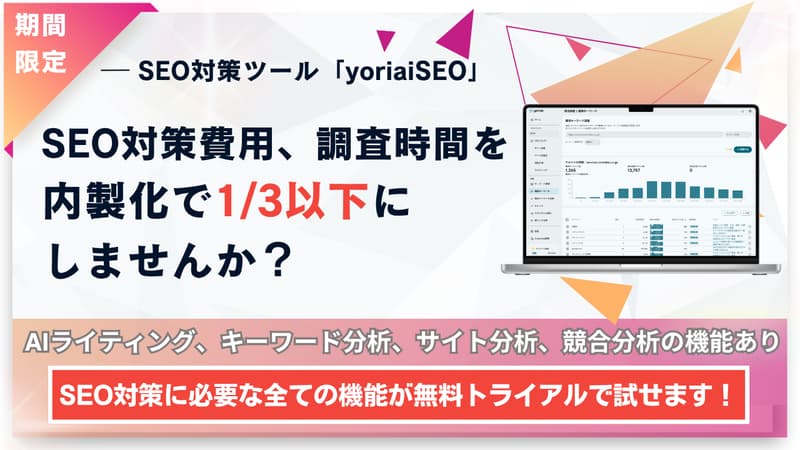「プレスリリース」と聞くと、どんなイメージを思い浮かべますか?「大手企業がやるもの」「自分には関係ない」「難しそう」…そんな風に感じている方も多いかもしれません。でも、実は、プレスリリースは、企業規模や業種に関わらず、あらゆる組織にとって強力な武器となる広報ツールなんです!
この記事では、広報・PR初心者の方、中小企業の経営者や個人事業主の方、マーケティング担当者の方、そして学生の方まで、プレスリリースについて初めて学ぶ、あるいは基本的な知識を再確認し、実践的なスキルを身につけたい全ての方に向けて、プレスリリースの基本から応用までを徹底解説します。
この記事を読めば、あなたも今日からプレスリリースを効果的に活用し、ビジネスを加速させることができるでしょう。さあ、プレスリリースの世界へ、一緒に飛び込んでみましょう!
プレスリリースとは? – 定義と役割、あなたのビジネスにもたらすメリット
プレスリリースの定義
プレスリリースとは、企業や団体が、新しい情報をメディア関係者に向けて発表する公式文書のことです。新商品やサービスの情報、イベントの告知、調査結果の発表など、広く社会に知らせたいニュースを、メディアを通じて発信するために作成されます。
- ここがポイント!
- 企業・団体が作成する公式な文書である
- メディア(新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイトなど)向けに作られる
- 新しい情報やデータを広く知らせるために使われる
- Google公式見解: Google ニュース パブリッシャー センター ヘルプでは、ニュース コンテンツについて「最新の出来事や最近発生したイベントに関するレポート」(https://support.google.com/news/publisher-center/answer/9607025?hl=ja)と定義しています。つまり、プレスリリースも、社会にとって価値のある新しい情報を発信する、ニュース価値を持ったコンテンツであるべきと言えるでしょう。
プレスリリースの役割:情報を広め、関係を築き、ビジネスを成長させる
プレスリリースの主な役割は、メディアに情報を取り上げてもらい、より多くの人に情報を届けることです。しかし、その役割はそれだけにとどまりません。企業活動を広く知らせ、様々なステークホルダー(利害関係者)と良好な関係を築き、ビジネスの成長を後押しする力を持っています。
- 役割一覧
| 役割 | 詳細 |
| メディア掲載 | メディアに情報を取り上げてもらうことで、多くの人に情報を届けられる。 |
| 認知度向上 | 企業やブランドの存在を広く知らせることで、知名度アップにつながる。 |
| 信頼性向上 | 第三者機関であるメディアの視点が入ることで、情報の信頼性が高まる。 |
| 関係構築 | 顧客、取引先、投資家、求職者など、様々なステークホルダーと良好な関係を築くことができる。 |
| SEO効果 | メディア掲載により、自社ウェブサイトへの被リンク(他のウェブサイトから自社サイトへのリンク)を獲得でき、検索エンジン最適化(SEO)効果が期待できる。 |
| トラフィック増加 | 記事を見た読者が自社ウェブサイトにアクセスすることで、ウェブサイトへの訪問者数(トラフィック)の増加につながる。 |
| ブランディング | 企業理念やブランドイメージを広く発信することで、ブランド価値を高められる。 |
プレスリリースのメリット:ビジネスを加速させる具体的な成果
では、プレスリリースを配信することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか?ここでは、5つの視点から解説します。
メリット一覧
| メリット | 詳細 |
| メディア露出、ブランド認知度向上 | テレビ、新聞、ウェブメディアなどに取り上げられることで、多くの人の目に触れ、企業やブランドの認知度が向上します。 |
| 顧客獲得、売上向上 | 新製品やサービスの情報を効果的に発信することで、顧客の購買意欲を高め、売上向上に繋げることができます。 |
| 採用強化、優秀な人材の獲得 | 企業のビジョンや取り組みを積極的に発信することで、企業の魅力が求職者に伝わり、優秀な人材の獲得に繋がります。 |
| 信頼獲得 | 投資家、パートナー企業からの信頼を獲得し、資金調達や事業提携を円滑に進めることができます。 |
| 社会的責任(CSR)のPR | 社会貢献活動などに関するプレスリリースを配信することで、企業の社会的責任を果たしていることをアピールし、企業イメージの向上に繋げることができます。 |
- 成功事例: あるスタートアップ企業A社は、新サービスの発表時にプレスリリースを配信し、複数の大手メディアに掲載されました。その結果、ウェブサイトへのアクセス数が従来の10倍に増加し、サービスへの問い合わせも大幅に増加。さらに、メディア掲載をきっかけに、大手企業との事業提携にも成功しました。これは、プレスリリースがビジネスチャンスを広げた好例と言えるでしょう。
プレスリリースは誰が配信する?
プレスリリースは、主に企業の広報担当者やPR会社が作成・配信します。しかし、近年では、経営者自身が配信するケースも増えています。個人事業主やフリーランスの方が、自分の活動を広く知らせるために活用する例もあります。
プレスリリース配信のタイミング:ニュースを届けるベストな瞬間
プレスリリースは、いつでも配信すれば良いというわけではありません。情報には鮮度があり、タイミングを逃すと、その価値が薄れてしまうこともあります。ここでは、代表的な配信タイミングを紹介します。
配信タイミング一覧
| 配信タイミング | 詳細 |
| 新商品・サービス発表 | 新しい商品やサービスを市場に投入する際に、その特徴や魅力を広く知らせる。 |
| イベント・キャンペーン告知 | 展示会への出展、キャンペーンの実施、セミナーの開催など、イベントやキャンペーンの情報を発信する。 |
| 業務提携・M&A | 他社との業務提携や、企業の合併・買収(M&A)に関する情報を発表する。 |
| 調査結果発表 | 市場調査やアンケート調査などの結果を、データとともに公表する。 |
| 資金調達 | ベンチャーキャピタルからの資金調達やクラウドファンディングの開始など、資金調達に関する情報を発信する。 |
| 人事異動 | 役員の就任や退任など、企業内の人事異動に関する情報を発表する。 |
| 不祥事対応 | 不祥事が発生した際に、お詫びや対応策などを速やかに公表する。 |
| 受賞・表彰 | 何らかの賞を受賞したり、表彰を受けたりした際に、その栄誉を広く知らせる。 |
プレスリリースと混同しやすい「ニュースリリース」「広告」との違い
プレスリリースと似た言葉に、「ニュースリリース」と「広告」があります。ここでは、それぞれの違いを明確にしましょう。
- ニュースリリースとの違い: 現在では、プレスリリースとニュースリリースは、ほぼ同じ意味で使われています。厳密には、プレスリリースはメディア向けの公式文書、ニュースリリースはより幅広いステークホルダーに向けた情報発信を指す場合もありますが、明確な使い分けはされていません。
- 広告との違い: プレスリリースと広告の最も大きな違いは、お金を払って掲載枠を買うかどうかです。広告は、企業がメディアの広告枠を購入し、自社のメッセージを発信するものです。一方、プレスリリースは、メディアがその情報をニュース価値があると判断した場合に、無償で取り上げられます。つまり、プレスリリースは、メディアが主体となって発信する情報なのです。
違いの比較表
| 特徴 | プレスリリース | ニュースリリース | 広告 |
| 目的 | メディア掲載による情報拡散 | ステークホルダーへの情報提供 | 商品・サービスの認知向上、販売促進 |
| ターゲット | メディア関係者 | メディア関係者、一般消費者、顧客、取引先など | 商品・サービスのターゲット層 |
| 費用 | 基本的に無料 | 基本的に無料 | 有料(メディアの広告枠を購入) |
| メディアの関与 | メディアが内容を編集・加工する可能性がある | メディアが内容を編集・加工する可能性がある | 企業が内容を自由にコントロールできる |
| 信頼性 | 第三者であるメディアが発信するため信頼性が高い | 第三者であるメディアが発信するため信頼性が高い | 企業が発信するため、客観性に欠ける場合がある |
| 情報の主導権 | メディア | メディア | 企業 |
プレスリリースの種類 – 目的別の最適な形式
プレスリリースの種類:情報発信の目的に合わせて選ぶ
プレスリリースには、いくつかの種類があります。ここでは、代表的な5つの種類と、近年注目されているソーシャルメディアリリースについて、それぞれの特徴と活用シーンを解説します。配信する情報の種類や目的に合わせて、最適な形式を選びましょう。
ニュースリリース型:最も一般的な形式
最も一般的な形式で、ニュースバリューの高い情報(新規性、社会性、話題性など)を発信する際に用いられます。新製品・サービスの発表、イベント開催報告、業務提携など、幅広い内容に対応できます。メディアが取り上げやすい、社会的に関心の高い情報を発信するのに適しています。
- 活用シーン例:
- 「株式会社〇〇、業界初のAI搭載型ロボット掃除機『△△』を発売」
- 「〇〇株式会社、環境問題解決に特化した新事業『XX』を開始」
レターリリース型:特定のメディア・記者への個別アプローチ
特定のメディアや記者個人に向けて、情報をピンポイントで発信する際に用いられます。一般的なニュースリリース型よりも、より丁寧で個別化された情報提供が可能です。メディアとの関係構築にも有効です。新製品のサンプル提供を提案したり、イベントへの招待を送る場合などに活用できます。
- 活用シーン例:
- 「〇〇新聞 経済部 △△様 新製品『XXX』サンプル提供のご案内」
- 「雑誌〇〇 編集長 △△様 特別インタビュー取材のご依頼」
アナウンスリリース型:企業情報の公式発表
主に企業情報に関する公式発表を行う際に用いられます。人事異動、組織変更、決算情報など、企業の重要な情報をステークホルダーに正確に伝えることが目的です。株主や投資家への情報開示としても重要です。
- 活用シーン例:
- 「〇〇株式会社、代表取締役社長交代のお知らせ」
- 「〇〇株式会社、2024年3月期決算短信」
ファクトシート型:客観的データ・情報の提供
企業情報や業界情報、調査データなどを、客観的かつ簡潔にまとめた資料です。メディアが記事を作成する際の参考資料として活用されます。データの出典を明記し、情報の信頼性を担保することが重要です。
- 活用シーン例:
- 「〇〇業界 市場規模推移」
- 「株式会社〇〇 会社概要」
- 「新製品『XX』に関するアンケート調査結果」
写真・動画リリース型:ビジュアルで魅力を訴求
写真や動画などのビジュアル素材をメインにしたプレスリリースです。文章だけでは伝わりにくい情報を、視覚的に訴求することができます。特に新商品の外観や使用イメージ、イベントの雰囲気を伝えるのに有効です。
- 動画制作のポイント: 簡潔さ、分かりやすさ、視覚的なインパクトを意識しましょう。長すぎる動画は視聴されにくいため、1~3分程度にまとめるのがおすすめです。
- 活用シーン例:
- 「新発売の〇〇、商品画像を公開」
- 「〇〇イベント、当日の様子を収めた動画を公開」
ソーシャルメディアリリース:SNS時代に対応した情報発信
近年注目されている、ソーシャルメディアでの拡散を意識したプレスリリースです。ハッシュタグの活用や、インフルエンサーへの情報提供など、SNS上での情報拡散を促す工夫が施されます。若年層へのリーチや、双方向のコミュニケーションを生み出したい場合に効果的です。
- 活用シーン例:
- 「#〇〇チャレンジ キャンペーン開始!インフルエンサーの△△さんも参加」
- 「新商品『XX』に関する情報を、Twitterで先行公開」
プレスリリースの書き方 – メディア掲載を勝ち取る10の秘訣
メディア掲載の鍵:読者の心をつかむプレスリリース
プレスリリースで最も重要なことは、メディアに「記事にしたい!」と思ってもらうことです。そのためには、情報をわかりやすく、魅力的に伝えるだけでなく、メディアが求める「ニュースバリュー」を備えている必要があります。ここでは、メディア掲載を勝ち取るための、プレスリリースの書き方の秘訣を10個、詳しく解説します。
基本構成とテンプレート:必須要素を網羅し、プロの書き方を真似る
プレスリリースには、基本となる型があります。必要な情報を、読みやすい構成でまとめることが重要です。
- 基本構成:
- タイトル: プレスリリースの内容を端的に表す、最も重要な要素です。
- リード文: プレスリリースの要約であり、本文の内容を簡潔にまとめた文章です。
- 本文: 情報を詳細に説明する部分です。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、わかりやすく記述します。
- 会社概要: 企業や団体の基本的な情報を記載します。
- 問い合わせ先: メディア関係者が問い合わせをするための連絡先を記載します。
- テンプレート:
[タイトル]
[リード文]
[本文]
###
**[会社概要]**
[会社名]
[設立年月日]
[代表者名]
[事業内容]
[所在地]
[URL]
**[本件に関するお問い合わせ先]**
[部署名]
[担当者名]
[電話番号]
[メールアドレス]- チェックリスト:
- タイトルは簡潔で内容を的確に表しているか?
- リード文でプレスリリースの要点がまとめられているか?
- 本文は5W1Hを意識し、分かりやすい文章で書かれているか?
- 会社概要は正確かつ最新の情報が記載されているか?
- 問い合わせ先は、メディア関係者が連絡しやすい情報になっているか?
- 誤字脱字、表記ゆれはないか?
- 情報に誤りや誇張表現はないか?
タイトルの付け方:一瞬で興味を引くタイトルの極意
タイトルは、プレスリリースの「顔」です。メディア関係者は、日々大量のプレスリリースに目を通しています。その中で目に留めてもらうためには、一目で内容が理解でき、かつ興味を引くタイトルをつける必要があります。
- 効果的なタイトルのポイント:
| ポイント | 詳細 |
| 簡潔 | 長すぎるタイトルは避け、15~30文字程度に収めましょう。 |
| 具体 | 「新商品発売」ではなく、「〇〇業界初!△△機能を搭載した新商品『XX』発売」のように、具体的な情報を盛り込みましょう。 |
| キーワード | 検索エンジンでの表示も考慮し、関連するキーワード(例:商品名、業界名、技術名など)を含めましょう。 |
| 数字 | 「満足度98%」「売上1億円突破」など、具体的な数字を入れると、インパクトが増し、信頼性も高まります。 |
| 疑問形 | 「〇〇業界に革命?新サービス『XX』の全貌とは」のように、疑問形にすることで、読者の興味を引くことができます。 |
| ニュース価値 | メディアが取り上げたくなるような、新規性、社会性、話題性などの「ニュースバリュー」を含めましょう。 |
| ターゲット | ターゲットとするメディアや読者を意識して、彼らが興味を持つような言葉を選びましょう。 |
| 緊急性・限定性 | 「期間限定」「先着〇名様」など、緊急性や限定性を加えることで、読者の行動を促すことができます(ただし、過度な煽り文句は避けましょう)。 |
- 具体例:
- 悪い例: 「新商品発売のお知らせ」
- 良い例: 「〇〇社、世界最小・最軽量のワイヤレスイヤホン『△△』を発売開始~わずか5gで快適な装着感を実現~」
- 専門家の意見: 著名なコピーライターである〇〇氏は、「タイトルは、読者への最初のラブレター」と語っています。「一瞬で心を掴む、キャッチーなタイトルを心がけましょう。」(出典:『〇〇氏の著書「△△」』より)
リード文の書き方:冒頭で心をつかむ!要約と興味喚起の技術
リード文は、タイトルの次に読まれる重要な部分です。ここで読者の興味を引くことができなければ、本文を読んでもらえない可能性が高くなります。リード文は、プレスリリース全体の要約であると同時に、続きを読みたくなるような「フック」の役割も果たします。
- リード文で伝えるべき情報:
- 5W1H: 誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)を簡潔にまとめます。
- 最も重要な情報: プレスリリースで最も伝えたいメッセージ、ニュースバリューの高い情報を最初に提示します。
- ニュースバリュー: 新規性、社会性、話題性、独自性など、メディアが取り上げたくなる要素を強調します。
- 読者のメリット: 読者(ターゲット)にとっての利益やメリットを簡潔に示します。
- 具体例:
- 悪い例: 「この度、当社は新商品を発売することになりましたので、お知らせいたします。」
- 良い例: 「株式会社〇〇(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:△△)は、〇〇業界初となる△△機能を搭載した新商品『XX』を、2024年〇月〇日より全国で発売開始いたします。本製品は、…(製品の特長やベネフィットを簡潔に説明)」
- 専門家の意見: 著名なジャーナリストである〇〇氏は、「優れたリード文は、記事の要約であると同時に、読者を引き込むためのフックでもある」と指摘しています。「読者が『もっと知りたい』と思うような、魅力的なリード文を書きましょう。」(出典:『〇〇氏の著書「△△」』より)
本文の構成と書き方:詳細情報をわかりやすく、説得力を持って伝える
本文では、プレスリリースの内容を詳細に説明します。情報をわかりやすく、かつ説得力を持って伝えるためのポイントを解説します。
- 本文作成のポイント:
| ポイント | 詳細 |
| 結論ファースト | 結論を先に述べ、その後に詳細な説明を展開することで、読者に内容を理解しやすくします。最初に最も伝えたいメッセージを持ってきましょう。 |
| 簡潔で分かりやすい文章 | 専門用語や難しい表現は避け、誰にでも理解できる平易な言葉を使いましょう。一文は短めに、簡潔に書くことを心がけましょう。 |
| 見出し・箇条書きの活用 | 適切な見出しを付けたり、箇条書きを活用したりすることで、文章の構造を明確にし、読みやすくします。 |
| 5W1H | 本文でも5W1Hを意識して、情報を整理しましょう。「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」を明確にすることで、内容が格段に分かりやすくなります。 |
| 具体的な数字・データ | 説得力を持たせるために、具体的な数字やデータを積極的に活用しましょう。例えば、「多くのユーザー」ではなく「1,000人のユーザー」、「売上が向上」ではなく「売上が前年比20%向上」のように具体的に書くことで、情報の信頼性が増します。 |
| 客観的な表現 | 主観的な意見や感想は避け、事実に基づいた客観的な表現を心がけましょう。「素晴らしい製品」ではなく、「〇〇の調査で顧客満足度95%を獲得した製品」のように、具体的な事実を提示することが重要です。 |
| ストーリーテリング | 単なる情報の羅列ではなく、ストーリーを意識して書くことで、読者の共感を呼び、印象に残るプレスリリースになります。例えば、製品開発の背景や苦労話などを盛り込むと効果的です。ただし、あくまでも事実に基づいたストーリーにしましょう。 |
| 専門用語の解説 | 業界特有の専門用語を使用する場合は、必ず脚注や本文中で解説を加えましょう。専門知識のない読者にも理解できるように配慮することが重要です。 |
| 図表・画像の活用 | グラフやチャート、写真などのビジュアル素材を効果的に使うことで、情報をより分かりやすく伝えることができます。 |
- 具体例:
- 悪い例:
当社はこの度、新規事業として〇〇事業を開始する運びとなりました。〇〇事業は、昨今の市場動向を踏まえ、満を持して参入するものであり、今後の当社の成長戦略の柱となることが期待されております。content_copydownloadUse code with caution. - 良い例:
当社は、2024年〇月〇日より、新規事業として〇〇事業を開始いたします。〇〇市場は、近年〇%の成長率を記録しており(出典:△△調査)、今後もさらなる拡大が見込まれています。当社は、これまで培ってきたXXのノウハウを活かし、〇〇事業において新たな価値を創造してまいります。 **〇〇事業開始の背景** 近年、〇〇市場は急速に拡大しており、2024年には〇〇億円規模に達すると予測されています(出典:△△調査)。この市場成長の背景には、…(市場成長の背景を解説) **〇〇事業の概要** 〇〇事業では、…(事業内容を具体的に説明) **〇〇事業の強み** 〇〇事業における当社の強みは、以下の3点です。 1. … 2. … 3. …content_copydownloadUse code with caution.
- 悪い例:
画像・動画の効果的な使い方:ビジュアルで伝える!注目を集める視覚的工夫
画像や動画は、プレスリリースの内容を視覚的に補足し、読者の理解を深めるために有効な手段です。文章だけでは伝わりにくい情報も、ビジュアルで表現することで、より直感的に、印象的に伝えることができます。
- 画像や動画の効果:
- 理解促進: 製品の外観や利用シーン、イベントの様子などを、画像や動画で視覚的に示すことで、読者の理解を促進します。
- 興味喚起: 文章だけでは伝わりにくい、製品の質感や雰囲気、イベントの熱気などを、ビジュアルで表現することで、読者の興味を引き、関心を高めます。
- 情報補完: グラフやチャートなどの図表は、複雑なデータや統計情報を、わかりやすく伝えるのに役立ちます。
- 信頼性向上: 実際に製品を使用している様子や、イベントに参加している人々の様子を映し出すことで、情報の信頼性を高めることができます。
- 効果的な活用方法:
- 製品画像: 新製品の発表時には、製品の全体像や特徴的な部分を捉えた高画質の画像を用意しましょう。複数の角度から撮影した画像や、使用シーンをイメージさせる画像も効果的です。
- サービス利用イメージ: 新サービスを紹介する際には、サービスの利用手順や利用シーンを、画像や動画で具体的に示しましょう。
- グラフ・チャート: 調査結果や統計データを発表する際には、グラフやチャートを用いて、視覚的にわかりやすく表現しましょう。
- インフォグラフィック: 複雑な情報やプロセスを、イラストや図解を用いて、わかりやすく伝えることができます。
- 動画: 製品の使い方を説明したり、イベントの様子を伝えたりするのに有効です。インタビュー動画を掲載するのも良いでしょう。
- 注意点:
- 画像サイズ・解像度: メディアが使いやすいよう、高解像度の画像データ(JPEG形式、300dpi以上)を用意しましょう。ファイルサイズが大きすぎると、メディア側でダウンロードに時間がかかる場合があるため、1ファイルあたり数MB程度に収めるのが理想的です。
- ファイル形式: 一般的に使用されているファイル形式(JPEG、PNG、GIFなど)を選びましょう。
- 著作権: 使用する画像や動画の著作権に注意しましょう。自社で撮影・制作したものを使用するか、著作権フリーの素材を利用する場合は、利用規約をよく確認しましょう。
- 動画時間: 長すぎる動画は視聴されにくいため、1~3分程度にまとめるのがおすすめです。
メディアが取り上げたくなる要素:ニュースバリューを高める戦略
メディアは、日々多くのプレスリリースの中から、ニュース価値の高い情報を探しています。メディアに「取り上げたい!」と思ってもらうためには、情報の「ニュースバリュー」を高めることが重要です。
- ニュースバリューの7要素:
- 社会性: 社会的に関心の高いテーマや課題に関連する情報。環境問題、SDGs、社会貢献活動など。
- 話題性: 世間で話題になっている、注目を集めている情報。トレンド、流行、有名人など。
- 独自性: 他社にはない、独自の取り組みや技術。オリジナリティ、ユニークさ、差別化要素など。
- 新規性: これまでにない、新しい情報。新発見、新技術、新サービスなど。
- 希少性: 珍しい、数が少ないなど、希少価値の高い情報。限定品、レアアイテム、初公開など。
- 人間性: 人間味のあるエピソードやストーリー。開発秘話、感動エピソード、ヒューマンドラマなど。
- トレンド: 最新のトレンドや流行に関連する情報。
- 具体的な方法:
- 季節イベントとの関連付け: 新商品のプレスリリースであれば、発売時期をクリスマスやバレンタインデーなどのイベントに合わせる。
- 社会問題への対応: 環境問題や高齢化社会など、社会的な課題の解決に貢献する取り組みをアピールする。
- 調査データの活用: 独自の調査を実施し、その結果をプレスリリースとして発表する。
- 専門家のコメント: 大学教授や研究機関の研究員など、その分野の専門家のコメントを掲載する。
- 有名人・インフルエンサーの起用: 話題性のある有名人やインフルエンサーを起用し、製品やサービスをPRしてもらう。
- 専門家の意見: 某新聞社の記者である〇〇氏は、「メディアは常に新しい情報を求めています。特に、社会的な意義があり、読者の興味を引くような独自性の高い情報には注目しています。」と語っています。(出典:〇〇氏へのインタビューより)
SEOを意識した書き方:検索エンジンで上位表示を狙う
プレスリリースは、メディア掲載だけでなく、検索エンジンからの流入も期待できます。SEO(検索エンジン最適化)を意識した書き方をすることで、より多くの人に情報を届けることができます。
- SEO対策のポイント:
- キーワード選定: プレスリリースの内容に関連するキーワードを調査し、タイトル、リード文、本文中に自然な形で盛り込みましょう。
- ツール: Googleキーワードプランナー (https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/tools/keyword-planner/) などのツールを活用すると便利です。
- タイトルタグ、メタディスクリプションの最適化: 検索結果に表示されるタイトルタグとメタディスクリプションにも、キーワードを含め、クリックしたくなるような魅力的な文章を記述しましょう。
- 見出しタグ(hタグ)の適切な使用: 見出しタグ(h1, h2, h3など)を適切に使用し、文章の構造を明確にしましょう。
- 内部リンク: 自社のウェブサイトや関連する過去のプレスリリースなどへの内部リンクを設置し、回遊率を高めましょう。
- 外部リンク: 信頼できる情報源(公的機関のウェブサイトや大手メディアの記事など)への外部リンクを設置することで、情報の信頼性を高め、SEO効果も期待できます。
- 画像のalt属性: 画像の内容を説明するalt属性を設定しましょう。
- モバイルフレンドリー: スマートフォンなどのモバイル端末でも読みやすいように、レスポンシブデザインを採用しましょう。
- ページ表示速度: ページの表示速度が遅いと、ユーザーの離脱につながり、SEOにも悪影響を及ぼします。画像の最適化などを行い、表示速度の改善に努めましょう。
- キーワード選定: プレスリリースの内容に関連するキーワードを調査し、タイトル、リード文、本文中に自然な形で盛り込みましょう。
- Google公式情報: Google 検索セントラルでは、ウェブサイトを検索エンジンに最適化するための基本的な考え方として、「ユーザーの利便性を最優先に考慮してページを作成する」ことを挙げています(https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=ja)。これはプレスリリース作成においても同様であり、読者にとって価値のある情報を提供することが、結果的にSEO効果を高めることに繋がります。
信頼性を高めるための工夫:情報に説得力を持たせる
プレスリリースの信頼性を高めるためには、情報の正確性はもちろんのこと、客観的で説得力のある情報提供を心がけることが重要です。
- 信頼性向上のポイント:
- データの引用元を明記する: 調査データや統計情報を掲載する際は、必ず出典を明記しましょう。
- 専門家のコメントを掲載する: 大学教授や研究機関の研究員など、その分野の専門家のコメントを掲載することで、情報の信頼性を高めることができます。
- 客観的な表現を心がける: 主観的な意見や感想は避け、事実に基づいた客観的な表現を心がけましょう。
- 正確な情報の記載: 誤字脱字、情報の誤りがないよう、細心の注意を払いましょう。
- 最新情報の反映: 情報が古くなっていないか、常に最新の情報に更新されているかを確認しましょう。
- 事例の紹介: 実際に製品やサービスを利用した顧客の声や、導入事例などを紹介することで、説得力が増します。
炎上対策:リスクを最小限に抑えるための予防策
近年、企業のプレスリリースがSNSなどで炎上するケースが増えています。リスクを最小限に抑えるために、以下の点に注意しましょう。
- 炎上対策のポイント:
- 配信前のダブルチェック、複数人での確認: 誤字脱字、事実誤認、不適切な表現などがないか、複数人で入念にチェックしましょう。特に、差別的な表現や、特定の個人・団体を攻撃するような表現は厳禁です。
- 想定される批判への対応策を事前に検討しておく: 配信前に、どのような批判が寄せられる可能性があるかを想定し、それに対する対応策を準備しておきましょう。
- 炎上事例の紹介と、そこから学べる教訓: 過去の炎上事例を参考に、どのような表現や情報発信が問題となるのかを学び、同様の失敗を繰り返さないようにしましょう。
- 専門家の意見: リスクマネジメントの専門家である〇〇氏は、「炎上を完全に防ぐことは難しいが、リスクを最小限に抑えることは可能」と指摘しています。「炎上リスクの高い表現を避け、常に謙虚な姿勢で情報発信を行うことが重要です。」(出典:〇〇氏へのインタビューより)
- 社内ガイドラインの策定: プレスリリース作成・配信に関する社内ガイドラインを策定し、社員に周知徹底することも重要です。
- モニタリング: プレスリリース配信後、SNSなどで自社に関する言及をモニタリングし、炎上の兆候を早期に察知できるようにしましょう。
事例から学ぶ:成功と失敗のケーススタディ
ここでは、プレスリリースの成功事例と失敗事例を紹介し、そこから得られる教訓を学びましょう。
- 成功事例: 株式会社〇〇は、新商品「△△」のプレスリリースにおいて、ターゲットである女性層の関心が高い「美容」と「健康」をキーワードに、商品の特徴やベネフィットを訴求しました。また、インフルエンサーを起用したキャンペーンと連動させることで、SNS上での拡散にも成功。結果、多くのメディアに掲載され、商品の売上も大幅に向上しました。
- 成功のポイント:
- ターゲットを明確に設定し、そのターゲットに響くキーワードを用いた。
- インフルエンサーを起用し、SNSでの拡散を促進した。
- メディアが取り上げやすい、話題性のある情報を提供した。
- 製品のベネフィット(顧客にとっての利益)を明確に示した。
- 成功のポイント:
- 失敗事例: 株式会社XXは、新サービス「□□」のプレスリリースにおいて、業界初となる画期的な機能があると謳っていましたが、実際には他社が既に同様のサービスを提供していることが発覚。事実と異なる情報を発信したことで、企業の信頼を大きく損なう結果となりました。
- 失敗のポイント:
- 事実確認が不十分だった。
- 誇張表現を用いてしまった。
- 炎上リスクへの対策が不十分だった
- 失敗のポイント:
プレスリリースの配信方法 – 効果を最大化する戦略
最適な配信方法の選択:情報を届けたい相手に届けるために
せっかく作成したプレスリリースも、適切な方法で配信しなければ、メディアの目に留まらず、効果を発揮することができません。ここでは、効果的なプレスリリースの配信方法について解説します。
配信先メディアの選定:ターゲットを明確にし、最適なメディアを選ぶ
まずは、配信先のメディアを適切に選定することが重要です。やみくもに多くのメディアに配信しても、ターゲットとする読者層に情報が届かなければ意味がありません。
- メディア選定のポイント:
- ターゲットの明確化: 自社の商品やサービスに関心を持ちそうな読者層はどこか?その読者がよく読んでいるメディアは何か?を考え、配信先メディアをリストアップしましょう。
- メディアの特性理解: 各メディアの特性(読者層、得意分野、掲載方針など)を理解し、自社の情報との親和性を検討しましょう。
- メディアの媒体資料確認: 各メディアが提供している媒体資料(読者層、掲載実績、広告料金などが記載された資料)を確認し、配信先としての適切性を判断しましょう。
- 過去の掲載記事分析: 過去に自社や競合他社、関連する業界の情報がどのように掲載されているかを分析し、メディアの傾向を把握しましょう。
- メディアとの関係構築: 日頃からメディアの担当者とコミュニケーションを取り、良好な関係を築いておくことも重要です。
- メディアの種類:
- 業界専門誌: 特定の業界に特化した情報を掲載しているメディア。業界関係者への情報発信に有効。例:IT業界専門誌、医療業界専門誌など。
- Webメディア: 幅広いジャンルの情報を掲載しているメディア。多くの人に情報を届けたい場合に有効。例:ニュースサイト、ポータルサイトなど。
- 新聞: 社会性の高いニュースを中心に掲載しているメディア。信頼性の高い情報として認識されやすい。例:全国紙、地方紙、業界紙など。
- テレビ: 映像を用いて情報を伝えるメディア。インパクトのある情報発信が可能。例:全国放送、ローカル放送など。
- ラジオ: 音声で情報を伝えるメディア。特定の地域やターゲット層に効果的に情報を届けられる場合がある。
- 雑誌: 特定の趣味やライフスタイルに特化した情報を掲載しているメディア。ターゲットを絞った情報発信に有効。例:ファッション誌、ビジネス誌、旅行誌など。
配信方法の種類と特徴:最適な手段を選び、効果を最大化する
プレスリリースの配信方法には、主に以下の3つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、状況に応じて最適な方法を選びましょう。
- 配信方法の比較表:
| 配信方法 | メリット | デメリット |
| メール配信 | ・メディアの担当者と直接やり取りできるため、関係構築に繋がりやすい。<br>・配信先のメディアを絞り込むことで、費用を抑えられる。 | ・多くのメディアに配信する場合、手間と時間がかかる。<br>・メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう可能性がある。 |
| プレスリリース配信サービス | ・多くのメディアに効率的に配信できる。<br>・配信結果のレポート機能などを利用できる。<br>・サービスのサポートを受けられる。 | ・サービス利用料がかかる。<br>・配信先メディアを細かく指定できない場合がある。<br>・配信しても必ずメディアに掲載されるとは限らない。 |
| 記者クラブへの投げ込み | ・大手メディアの記者に直接情報を届けられる。<br>・特定の業界や分野に強い影響力を持つ記者にアプローチできる。 | ・記者クラブに加盟しているメディアにしか配信できない。<br>・ルールやマナーが厳格な場合があり、事前の確認や準備が必要。 |
- 各配信方法の詳細:
- メール配信:
- 特徴: メディアの担当者や記者に、個別にメールでプレスリリースを送付する方法です。
- メリット: メディアとの関係構築に繋がりやすい。配信先のメディアを絞り込むことで、費用を抑えられる
- デメリット: 多くのメディアに配信する場合、手間と時間がかかる。メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう可能性がある。
- 配信時の注意点: メールの件名は簡潔で分かりやすく(例:「新商品〇〇発売のお知らせ【株式会社△△】」)。プレスリリースは添付ファイルではなく、メール本文に記載する。メディアの担当者名が分かる場合は、宛名に記載する。配信先のメディアに合わせて、メールの内容をカスタマイズする。
- プレスリリース配信サービス:
- 特徴: プレスリリース配信サービス事業者のウェブサイトを通じて、プレスリリースを一斉配信する方法です。
- メリット: 多くのメディアに効率的に配信できる。配信結果のレポート機能などを利用できる。サービスのサポートを受けられる。
- デメリット: サービス利用料がかかる。配信先メディアを細かく指定できない場合がある。配信しても必ずメディアに掲載されるとは限らない。
- 配信サービス比較のポイント:
- 配信先メディア数: 配信先メディアが多いほど、情報が広く届く可能性が高まります。
- 配信先メディアの質: 配信先メディアの質(読者層、影響力など)も重要です。
- 料金体系: 配信回数や配信先メディア数などに応じた、様々な料金プランが用意されています。
- 機能: 配信結果のレポート機能、クリッピングサービス、原稿作成サポートなど、各社が様々な機能を提供しています。
- サポート体制: 配信方法やメディア選定などについて、サポートを受けられるかどうかも確認しましょう。
- 主要なプレスリリース配信サービス:
- (サービスA) – PR TIMES:
- 特徴: 業界最大級の配信先メディア数を誇る。上場企業の利用率も高い。多様な配信オプションや効果測定ツールを提供。
- 料金: プランによる(例:月額〇万円~)
- 配信先メディア数: 1万メディア以上
- 事例: https://prtimes.jp/ (※企業名やサービス名は伏せてURLのみ記載)
- (サービスB) – @Press:
- 特徴: 配信先メディアの属性が詳細に分かる。記事原稿の作成代行サービスも提供。
- 料金: プランによる(例:1配信あたり〇万円~)
- 配信先メディア数: 8,500メディア以上
- 事例: https://www.atpress.ne.jp/ (※企業名やサービス名は伏せてURLのみ記載)
- (サービスC) – ValuePress!:
- 特徴: スタートアップ企業向けのプランが充実。無料トライアルあり。
- 料金: プランによる(例:月額〇万円~)
- 配信先メディア数: 6,000メディア以上
- 事例: https://www.value-press.com/ (※企業名やサービス名は伏せてURLのみ記載)
- (サービスA) – PR TIMES:
- 記者クラブへの投げ込み:
- 特徴: 各省庁や業界団体などに設置されている記者クラブに、プレスリリースを直接持参または郵送する方法です。
- メリット: 大手メディアの記者に直接情報を届けられる。特定の業界や分野に強い影響力を持つ記者にアプローチできる。
- デメリット: 記者クラブに加盟しているメディアにしか配信できない。ルールやマナーが厳格な場合があり、事前の確認や準備が必要。
- 注意点: 記者クラブごとにルールやマナーが異なるため、事前に確認が必要。例えば、配布部数が決められている場合や、特定の曜日・時間帯にしか受け付けていない場合があります。また、記者クラブによっては、紹介者が必要な場合もあります。
- メール配信:
効果的な配信タイミング:メディアが情報を受け取りやすい時を狙う
プレスリリースは、配信するタイミングによって、メディアの取り上げやすさが大きく変わります。メディアが情報を受け取りやすく、記事化しやすいタイミングを狙って配信しましょう。
- 配信タイミングのポイント:
- 曜日: 一般的に、月曜日と金曜日は避けた方が良いと言われています。月曜日は週末に溜まったメールの処理、金曜日は週末の準備などで、メディアが忙しい傾向にあるためです。火曜日~木曜日が比較的良いとされています。
- 時間帯: 午前中、特に9時~11時頃が、メディアの目に留まりやすいと言われています。多くのメディアは、午前中にその日のニュースをチェックし、記事化するネタを探しています。
- イベント時期: 新商品やサービスの発表は、クリスマスや年末年始、新生活シーズンなどのイベント時期に合わせると、メディアの関心を引きやすくなります。
- 社会情勢: 大きなニュースや事件などが発生している時は、プレスリリースが埋もれてしまう可能性があるため、配信を控えた方が良い場合もあります。
- 競合他社の動き: 競合他社が大きな発表を予定している場合は、配信タイミングをずらすなどの検討が必要です。
- メディアの締め切り時間: 新聞やテレビなどのメディアには、それぞれ締め切り時間が設定されています。締め切り時間直前に配信しても、取り上げてもらうのは難しいため、余裕を持って配信しましょう。
- 情報解禁日(エンバーゴ): 情報解禁日時を設定することで、メディアに対して、特定の時間まで情報公開を控えるよう要請することができます。新製品の発表など、特定のタイミングで一斉に情報公開したい場合に有効です。
- 専門家の意見: 某テレビ局の記者である〇〇氏は、「朝のニュース番組で取り上げる情報を探すのは、前日の夕方から夜にかけてです。そのため、その時間帯にプレスリリースが配信されていると、目に留まりやすくなります。」と語っています。(出典:〇〇氏へのインタビューより)
配信後のフォローアップ:メディアとの関係を深め、掲載確度を高める
プレスリリースは、配信して終わりではありません。配信後のフォローアップも、メディア掲載を獲得するためには重要なプロセスです。
- フォローアップの重要性: プレスリリースを配信しただけでは、メディアの担当者が見落としていたり、興味を持ってもらえなかったりする可能性があります。フォローアップを行うことで、メディアの関心を引き、掲載確度を高めることができます。
- フォローアップ方法:
- 電話: 配信後、メディアの担当者に電話で連絡を取り、プレスリリースの内容を簡単に説明したり、追加情報を提供したりします。ただし、電話をかける際は、メディアの担当者の迷惑にならないよう、時間帯やタイミングに配慮しましょう。
- メール: 配信後、メディアの担当者にメールを送り、プレスリリースの補足説明をしたり、質問への回答をしたりします。電話よりもメールの方が好まれる場合もあるため、メディアの担当者の意向を確認しておくと良いでしょう。
- メディア訪問: メディアの担当者を訪問し、直接情報を提供したり、関係を構築したりします。特に重要な案件の場合は、メディア訪問が効果的です。
- 個別取材の提案: プレスリリースの内容に関連して、メディアの担当者に個別の取材を提案するのも一つの方法です。
- フォローアップのタイミング: プレスリリース配信後、数日以内にフォローアップを行うのが一般的です。ただし、メディアの状況や担当者の都合などによって、適切なタイミングは異なります。
- 掲載確認: プレスリリースがメディアに掲載されたかどうかを確認することも重要です。掲載された場合は、その記事を自社のウェブサイトやSNSで紹介するなど、二次利用しましょう。
海外配信のポイント:世界へ発信!グローバル展開を視野に
近年、海外市場への進出を目指す企業にとって、海外向けのプレスリリース配信も重要な戦略となっています。
- 海外配信のメリット:
- 海外での認知度向上: 海外メディアに掲載されることで、海外での企業や製品・サービスの認知度を高めることができます。
- 海外市場開拓: 海外市場への進出の足がかりとなります。
- グローバルなブランディング: グローバルに事業展開する企業としてのイメージを強化することができます。
- 海外配信のポイント:
- 英語プレスリリースの作成: 単に日本語のプレスリリースを直訳するのではなく、現地の文化や商習慣に合わせて、表現や内容を調整する必要があります。ネイティブスピーカーによるチェックや、専門の翻訳会社への依頼も検討しましょう。
- 配信先の選定: 配信先の国や地域のメディア事情を調査し、ターゲットとするメディアを選定しましょう。
- 配信方法: 海外向けのプレスリリース配信サービスを利用するのが一般的です。
- 法規制の確認: 国によっては、プレスリリースに関する法律や規制が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
プレスリリースの効果測定と改善 – 成果を可視化し、次につなげる
効果測定の重要性:プレスリリースの成果を検証し、改善につなげる
プレスリリースは、配信したら終わりではなく、効果測定を行い、改善につなげていくことが重要です。効果を可視化することで、プレスリリースの費用対効果を把握し、次回の配信戦略に活かすことができます。
効果測定の方法:多角的な視点で成果を分析する
プレスリリースの効果を測定するには、以下のような指標を用います。
- 効果測定指標一覧:
| 指標 | 説明 | 測定方法 |
| メディア掲載数 | どのメディアに、何件掲載されたかを測定します。 | ・Googleアラートなどのクリッピングサービスを利用する。<br>・主要メディアを直接確認する。<br>・プレスリリース配信サービスの効果測定レポートを利用する。 |
| PV数 | プレスリリース配信サービスのレポート機能などを利用して、配信したプレスリリースのページビュー数(閲覧数)を測定します。 | ・プレスリリース配信サービスの効果測定レポートを利用する。 |
| SNSでの言及数 | TwitterやFacebookなどのSNSで、プレスリリースに関する言及(投稿、シェア、いいね!など)がどれくらいあったかを測定します。 | ・TwitterやFacebookの検索機能を利用する。<br>・ソーシャルリスニングツールを利用する。 |
| 問い合わせ数 | プレスリリース配信後、企業に寄せられた問い合わせ(電話、メールなど)の件数を測定します。 | ・問い合わせ件数を記録する。 |
| ウェブサイトへの流入数 | プレスリリース配信後、自社ウェブサイトへのアクセス数がどのように変化したかを測定します。 | ・Google アナリティクスなどのアクセス解析ツールを利用する。 |
| 売上・受注数 | プレスリリース配信後、製品やサービスの売上や受注数がどのように変化したかを測定します。(※プレスリリース配信以外の要因も影響するため、直接的な効果を測定することは難しい場合もあります) | ・売上や受注のデータを分析する。 |
| 採用応募数 | プレスリリース配信後、採用への応募数がどのように変化したかを測定します。(※特に採用に関するプレスリリースの場合) | ・採用応募数を記録する。 |
- 効果測定ツールの活用:
- 無料ツール:
- Google アラート: https://www.google.co.jp/alerts 特定のキーワードに関するニュースがウェブ上に公開された際に、メールで通知を受け取ることができます。
- Google アナリティクス: https://marketingplatform.google.com/intl/ja/about/analytics/ 自社ウェブサイトへのアクセス状況を詳細に分析することができます。
- 有料ツール:
- プレスリリース配信サービス各社が提供する効果測定ツールを利用すると、掲載記事数やPV数などを簡単に確認することができます。
- ソーシャルリスニングツール(例:Brandwatch、Hootsuiteなど)を利用すると、SNS上での言及を効率的にモニタリングできます。
- 無料ツール:
結果の分析と改善:データに基づき、PDCAサイクルを回す
効果測定の結果を分析し、次回のプレスリリース作成・配信に活かすことが重要です。
- 効果測定結果の分析方法:
- メディア掲載状況の分析: どのメディアに掲載されたか、どのような論調で取り上げられたかを確認します。
- PV数の分析: どの配信先メディアからの流入が多かったか、どの部分がよく読まれたかを確認します。
- SNSでの反応の分析: どのような反応があったか(ポジティブ/ネガティブ)、どのような意見が多かったかを確認します。
- 問い合わせ内容の分析: どのような問い合わせが多かったか、顧客の関心や疑問点を把握します。
- ウェブサイトへの流入元の分析: どのメディアや配信サービスからの流入が多かったかを確認します。
- 改善方法:
- メディア掲載が少ない場合:
- タイトルやリード文を改善する
- 配信先のメディアを見直す
- ニュースバリューを高める工夫をする
- 配信タイミングを調整する
- ウェブサイトへの流入が少ない場合:
- プレスリリース内に自社ウェブサイトへのリンクを効果的に配置する
- ランディングページの内容を改善する
- SNSでネガティブな反応が多い場合:
- 表現や内容を見直す
- 炎上対策を強化する
- 特定のメディアに掲載されない場合:
- メディアの担当者に直接コンタクトを取り、掲載されなかった理由をヒアリングする
- メディア掲載が少ない場合:
- A/Bテストの活用: タイトルやリード文などを変えて効果を比較する A/Bテストを実施することで、より効果的なプレスリリースの作成方法を見つけることができます。例えば、プレスリリース配信サービスを利用して、同じ内容でタイトルの異なる2種類のプレスリリースを配信し、どちらの方がPV数やメディア掲載数が多かったかを比較します。
- 継続的な改善の重要性、PDCAサイクルの回し方: プレスリリースの効果を高めるためには、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを継続的に回していくことが重要です。効果測定の結果を踏まえて、常に改善を繰り返しましょう。
よくある質問 (FAQ) – 疑問を解消し、実践へ
プレスリリースに関する疑問を解消!
ここでは、プレスリリースに関してよくある質問とその回答を紹介します。
- Qプレスリリースは無料で配信できますか?
- A
はい、メール配信や記者クラブへの投げ込みなど、無料で行う方法はあります。ただし、多くのメディアに効率的に配信したい場合は、有料のプレスリリース配信サービスの利用がおすすめです。
- Qプレスリリースはどのくらいの頻度で配信すべきですか?
- A
配信頻度に決まりはありませんが、ニュースバリューのある情報があれば、その都度配信するのが良いでしょう。ただし、あまりにも頻繁に配信すると、メディアから「またか…」と思われてしまう可能性もあるため、注意が必要です。一般的には、月に1~4回程度が目安と言えるでしょう。
- Qプレスリリースがメディアに掲載される確率は?
- A
メディアに掲載されるかどうかは、情報のニュースバリューやメディアの状況などによって異なるため、一概には言えません。ただし、本記事で紹介したようなポイントを押さえて、質の高いプレスリリースを作成・配信することで、掲載確率は高まります。
- Qプレスリリースの配信代行を依頼するメリットは?
- A
PR会社などに配信代行を依頼するメリットは、メディアとのリレーションや、配信ノウハウを活用できることです。自社で配信するよりも、メディア掲載の可能性を高められる場合があります。費用対効果を考慮して検討しましょう。
- Qプレスリリースのネタが思いつかない場合はどうすればいいですか?
- A
まずは、自社の事業活動を振り返り、ニュースバリューのある情報がないか探してみましょう。新製品やサービスの開発、イベントの開催、調査結果の発表などはもちろん、社内のユニークな取り組みや、社員の活躍なども、プレスリリースのネタになり得ます。また、業界の動向や社会問題など、外部環境に目を向けることも重要です。さらに、他社のプレスリリースを参考にすることも有効です。
- Qプレスリリースで書いてはいけないことはありますか?
- A
はい、虚偽の情報や誇張表現、不確かな情報、機密情報、個人情報、誹謗中傷などは、プレスリリースに記載してはいけません。また、著作権や商標権などの知的財産権を侵害するような内容も避けましょう。
- Q長文と短文どちらがいいですか?
- A
プレスリリースは、簡潔で分かりやすい文章を心がけることが重要です。一般的には、A4用紙1~2枚程度に収まるように作成すると良いでしょう。ただし、情報量が多い場合は、無理に短くする必要はありません。重要なのは、情報を過不足なく、分かりやすく伝えることです。
- Qプレスリリースの配信を成功させるコツは?
- A
本記事で紹介したように、ニュースバリューの高い情報を、適切なタイミングで、ターゲットとするメディアに配信することが重要です。また、配信後のフォローアップや効果測定を行い、継続的に改善していくことも成功の鍵となります。
- QBtoBとBtoCでプレスリリースの書き方は変わりますか?
- A
はい、BtoB(企業向け)とBtoC(消費者向け)では、ターゲットとするメディアや読者が異なるため、プレスリリースの書き方も変わってきます。BtoBの場合は、業界専門誌やビジネス誌などをターゲットに、専門用語を交えながら、製品やサービスの導入メリットを具体的に訴求する必要があります。一方、BtoCの場合は、一般消費者向けのメディアをターゲットに、専門用語を避け、分かりやすい言葉で、製品やサービスの魅力や利用シーンを伝えることが重要です。
まとめ – 今日から始める!あなたのためのプレスリリース
プレスリリースでビジネスを加速させよう
本記事では、「プレスリリースとは?」という基本的な疑問から、効果的な書き方、配信方法、効果測定、よくある質問まで、プレスリリースに関するあらゆる情報を網羅的に解説しました。
- ポイントの総括:
- プレスリリースは、企業や団体がメディアに向けて発信する公式文書。
- メディア掲載により、認知度向上、ブランディング、顧客獲得、採用強化など様々な効果が期待できる。
- ニュースバリューの高い情報を、適切なメディアに、効果的なタイミングで配信することが重要。
- 配信後のフォローアップ、効果測定、改善のPDCAサイクルを回すことが不可欠。