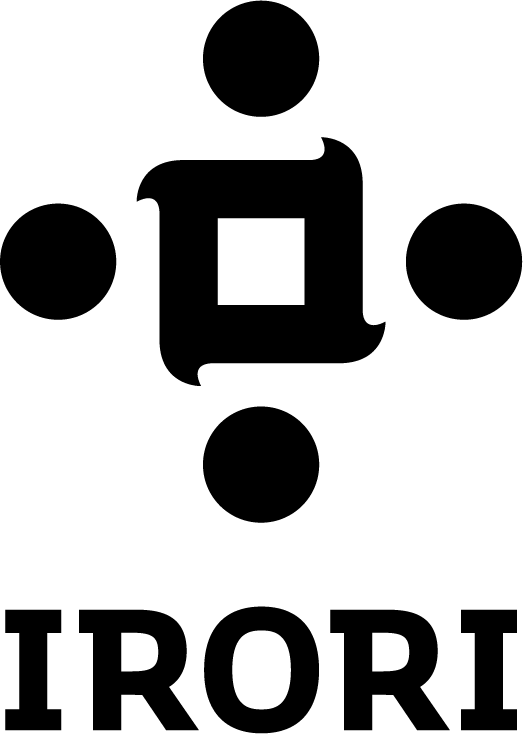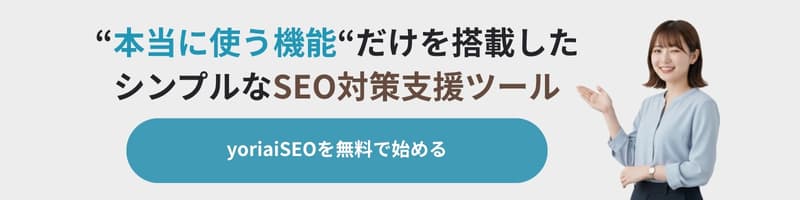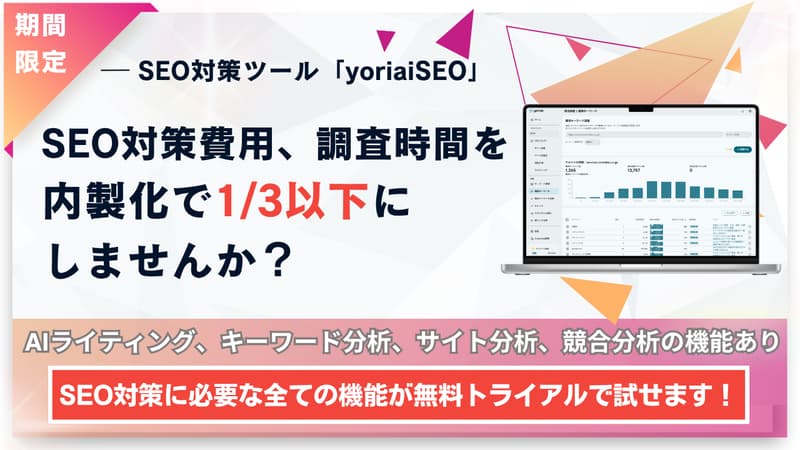テキスや画像から、まるで魔法のように動画を生み出す「動画生成AI」。OpenAIの「Sora」やGoogleの「Veo」といった革新的なツールの登場により、誰もが映像クリエイターになれる時代が到来しました。
しかし、その一方で「どのツールを使えばいいの?」「料金は?」「商用利用はできる?」「著作権は大丈夫?」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなあなたのための完全ガイドとして、主要な動画生成AIツールの特徴、料金、使い方を徹底比較します。さらに、最も気になる「著作権」の問題について、文化庁の見解や国内外の判例を交えながら、安心して利用するための知識を詳しく解説します。
【2025年6月最新】主要動画生成AIツールを徹底比較
現在、数多くの動画生成AIツールが登場し、それぞれが独自の特徴を持っています。ここでは、特に注目度の高い6つのツールをピックアップし、機能、料金、使い方などを比較します。
Sora (OpenAI)

ChatGPTで知られるOpenAIが開発した、動画生成AIの代名詞的存在。テキスト指示だけで、物理法則を理解したかのような非常にリアルで高品質な動画を生成できるのが最大の特徴です。
- 公式サイト: https://openai.com/sora/
- 日本語対応: プロンプト(指示文)、UIともに日本語に対応しています。
- 主な機能: テキストや画像、既存の動画から新しい動画を生成できます。動画内の要素を入れ替える「Remix」や、シーンを延長する「Re-cut」など、多彩な編集機能も搭載しています。
- 使い方: ChatGPTの有料プランに登録後、公式サイト「sora.com」にアクセスして利用します。
- 料金プランと商用利用: ChatGPTの有料プラン「Plus」(月額20ドル)または「Pro」(月額200ドル)に加入することで利用できます。生成した動画は商用利用が可能ですが、OpenAIの利用規約とコンテンツポリシーを遵守する必要があります。
- 生成できる動画: 長さは最大20秒(Proプラン)、解像度は最大1080pです。
Veo (Google)
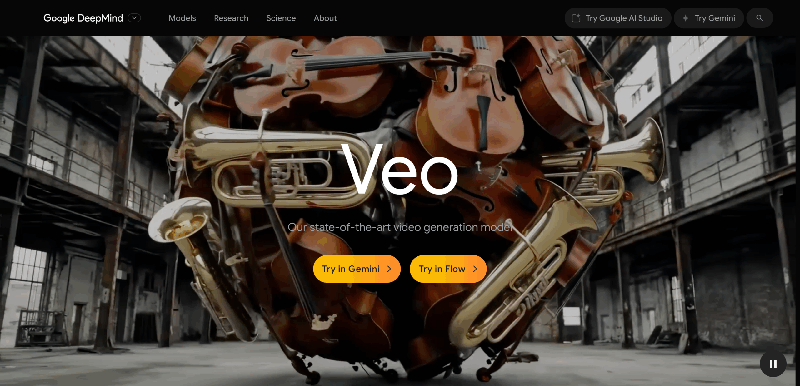
Googleが開発したSoraの強力な対抗馬。最新モデル「Veo 3」は、1分を超える高解像度動画の生成能力に加え、映像に合わせた音声(会話、BGM、効果音)も同時に生成できる点が画期的です。
- 公式サイト: https://deepmind.google/models/veo/
- 日本語対応: プロンプト、UIともに日本語に対応しています。
- 主な機能: 映像と音声を同時に生成できるほか、1分を超える1080pの高解像度動画を生成可能です。生成した動画の一部だけを再編集する「マスク編集」や、タイムラプス、ドローン空撮といった映画的な表現も得意としています。
- 使い方: 現在、Googleの「VideoFX」や「Gemini」アプリを通じて一部ユーザーに提供されています。公式サイトからウェイトリストに登録することで、利用機会を得られる可能性があります。
- 料金プランと商用利用: Google One AI Proプラン(月額19.99ドル)などで限定的に利用可能です。商用利用の可否はGoogleの利用規約に準じますが、著作権侵害のリスクには注意が必要です。
- 生成できる動画: 長さは1分以上、解像度は1080p(理論上4Kも可能)です。
Runway
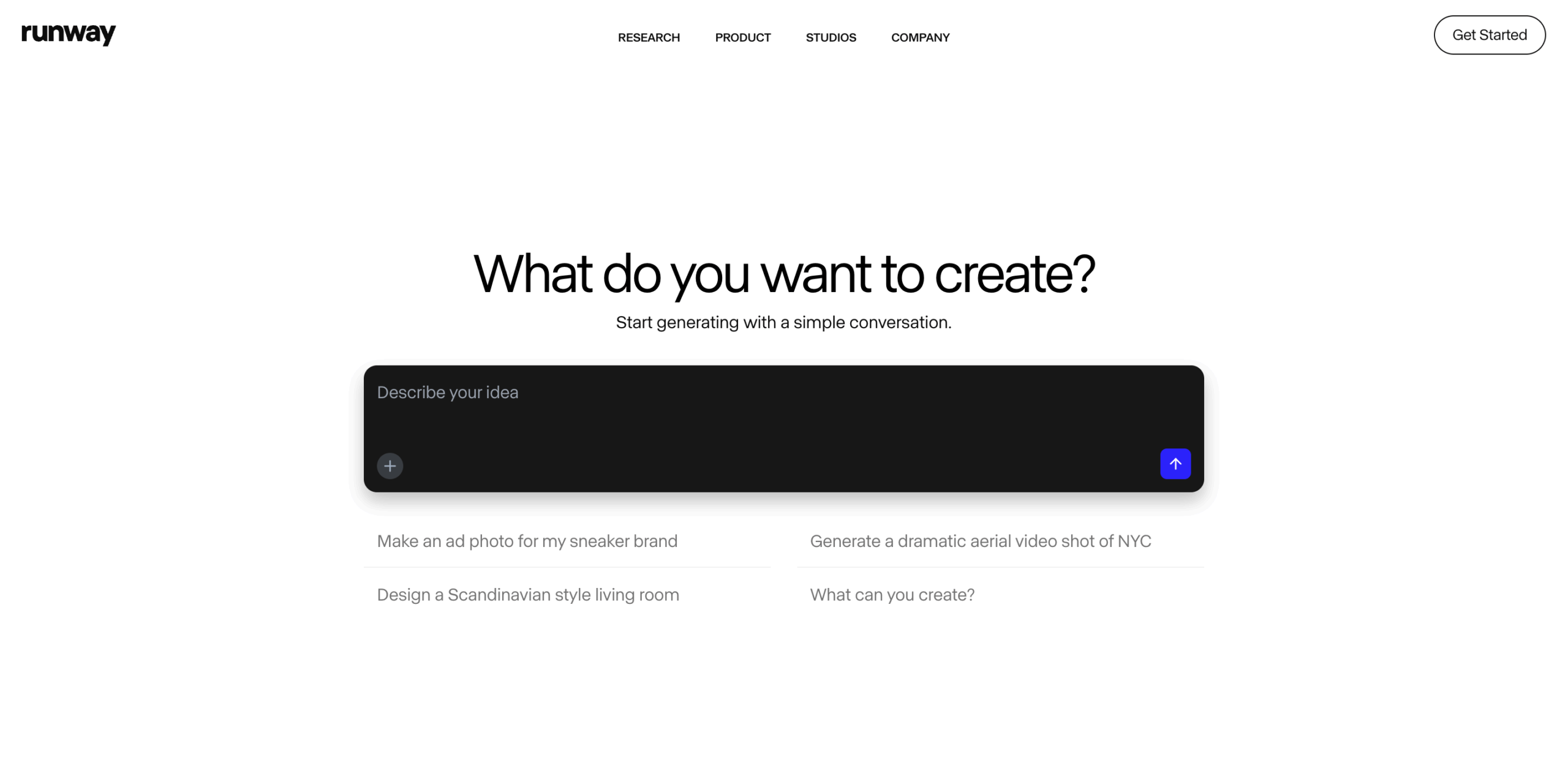
プロから初心者まで幅広く支持される動画生成・編集プラットフォーム。最新モデル「Runway Gen-4」は、物語性のあるコンテンツ生成能力が向上しています。
- 公式サイト: https://runwayml.com/
- 日本語対応: UIは英語のみですが、一部の音声生成機能では日本語に対応しています。プロンプトは英語での入力が推奨されます。
- 主な機能: テキストや画像からの動画生成に加え、カメラの動きを細かく制御する「Director Mode」や、参照画像のスタイルを動画に適用する「Stylization」など、プロ向けの機能が豊富です。
- 使い方: 公式サイトにアクセスし、アカウントを登録するだけで利用を開始できます。
- 料金プランと商用利用: 無料プランではクレジット制でウォーターマークが付きますが、有料プラン(月額12ドル〜)ではクレジット量が増え、ウォーターマークなしでの利用が可能です。全てのプランで商用利用が認められており、生成物の著作権はユーザーに帰属します。
- 生成できる動画: 長さは最大16秒、解像度は最大4K(有料プラン)です。
Pika
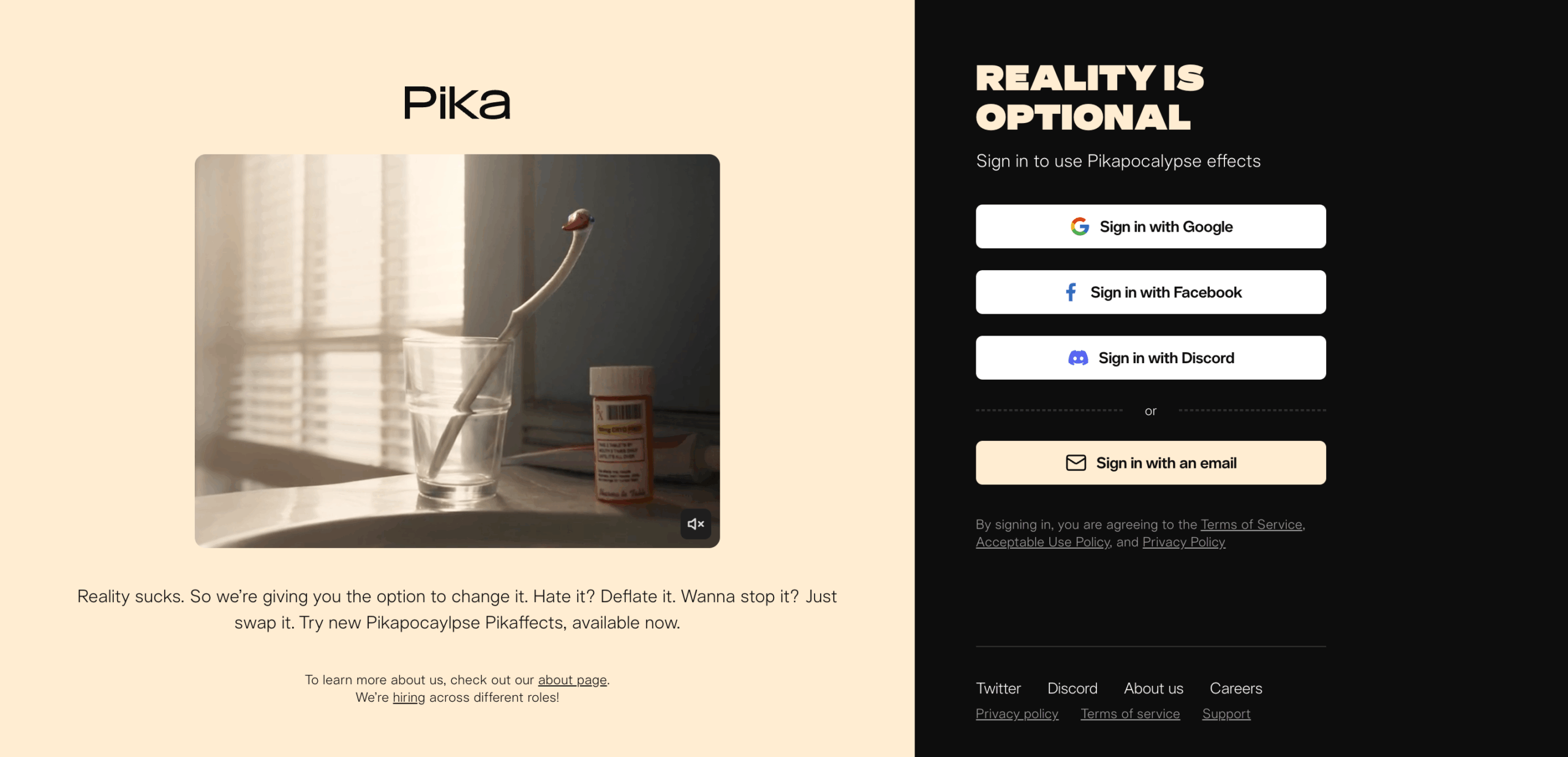
直感的なUIとユニークな編集機能で人気のツール。最新モデル「Pika 2.2」では、さらに多様な表現が可能になっています。
- 公式サイト: https://pika.art/
- 日本語対応: UIは英語ですが、プロンプトは日本語でも入力可能です(ただし英語の方が高精度)。
- 主な機能: 生成した動画の一部を再編集したり、動画を4秒ずつ延長したりできます。音声に合わせて口の動きを生成する「Lip-Sync」や、動画内のオブジェクトを入れ替える「Pikaswaps」などのユニークな機能も特徴です。
- 使い方: 公式サイトまたはチャットアプリ「Discord」から利用できます。
- 料金プランと商用利用: 無料プランでは毎日30クレジットが付与されますが、ウォーターマークが付きます。有料プランは月額10ドルから。商用利用は最上位の「Pro」プラン(月額70ドル)でのみ可能です。
- 生成できる動画: 基本の長さは3秒ですが、延長機能で長くすることが可能です。
Stable Video Diffusion (Stability AI)
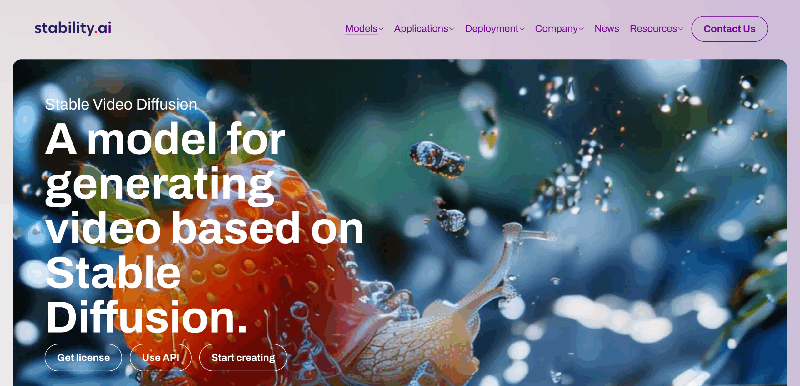
画像生成AI「Stable Diffusion」で有名なStability AIが開発したモデル。最新版「Stable Video 4D 2.0」では、単一動画からの3D的な視点生成も可能になっています。オープンソースで公開されているため、技術者が自身のPC環境で実行できる点が特徴です。
- 公式サイト: https://stability.ai/stable-video
- 日本語対応: UIは英語です。画像からの生成がメインのため言語はあまり関係ありませんが、関連ツールでのプロンプトは英語が基本です。
- 主な機能: 1枚の静止画から短い動画クリップを生成します。モデルが公開されており、ローカル環境やGoogle Colabなどで実行可能です。
- 使い方: Google ColabやHugging Faceなどのプラットフォーム上で、公開されているコードを実行して利用します。
- 料金プランと商用利用: 2024年7月にライセンスが更新され、「Community License」の下で、年間収益100万ドル未満の個人・企業は無料で商用利用が可能になりました。これを超える企業は有料のEnterpriseライセンスが必要です。
- 生成できる動画: 長さは約1〜5秒(14または25フレーム)、解像度は1024×576ピクセルが推奨されます。
Luma AI Dream Machine

テキストや画像から高品質な動画を高速生成できると話題のツール。2025年6月には、既存の動画を再編集する新機能「Modify Video」が追加されました。
- 公式サイト: https://lumalabs.ai/dream-machine
- 日本語対応: UIは英語ですが、プロンプトは日本語でも入力可能です(ただし英語の方が高精度とされています)。
- 主な機能: 5秒の動画を約2分で生成する高速性が特徴です。テキストだけでなく画像からも動画を生成でき、1枚の画像から一貫したキャラクターが登場する様々なシーンを作ることもできます。
- 使い方: 公式サイトにGoogleアカウントでログインするだけで利用を開始できます。
- 料金プランと商用利用: 無料プランでは月に30回まで生成可能ですが、ウォーターマークが付き、商用利用はできません。有料プラン(月額29.99ドル〜)に加入すると商用利用が可能になります。
- 生成できる動画: 長さは5秒、解像度は1360×752ピクセルです。
表1: 主要な動画生成AIツール比較(2025年6月時点)
| ツール名 | 日本語対応 | 無料プラン | 商用利用 | 公式サイトURL |
| Sora | 対応 | なし (ChatGPT有料プラン) | 可能 (要規約遵守) | https://openai.com/sora/ |
| Veo 3 | 対応 | 一部あり (Waitlist制) | 可能 (要規約遵守) | https://deepmind.google/models/veo/ |
| Runway Gen-4 | 一部対応 | あり (クレジット制) | 全プランで可能 | https://runwayml.com/ |
| Pika 2.2 | 一部対応 | あり (クレジット制) | Proプランのみ | https://pika.art/ |
| Stable Video 4D 2.0 | 非対応 | あり | 条件付きで無料可 | https://stability.ai/stable-video |
| Luma AI Dream Machine | 一部対応 | あり (回数制限) | 有料プランのみ | https://lumalabs.ai/dream-machine |
動画のクオリティを劇的に上げる!プロンプト作成3つのコツ
思い通りの動画を作るには、AIへの「指示書」であるプロンプトが極めて重要です。以下の3つのコツを押さえるだけで、生成される動画のクオリティは格段に向上します。
コツ1:具体的かつ詳細に描写する
AIは曖昧な言葉を苦手とします。「きれいな風景」ではなく、「夕日に照らされた、穏やかな波が打ち寄せる砂浜、遠くに灯台が見える」のように、5W1Hを意識して具体的に描写しましょう。
コツ2:要素を分解してAIに伝える
プロンプトを以下の要素に分けて考えると、AIが理解しやすくなります。
- 被写体 (Subject):
a fluffy cat(ふわふわの猫) - 行動 (Action):
sleeping on a bookshelf(本棚の上で眠っている) - 背景 (Setting):
in a cozy, sunlit room(日当たりの良い、居心地のいい部屋で) - スタイル (Style):
cinematic, 4K, photorealistic(映画風, 4K, 写真のようにリアル) - カメラワーク (Camera Work):
close-up shot(クローズアップ),drone shot(ドローン撮影)
コツ3:シンプルに始めて徐々に複雑にする
いきなり完璧なプロンプトを目指す必要はありません。まずは「a cat is running」のようなシンプルな指示から始め、生成された結果を見ながら「in the park」「at night」といった要素を付け加えていくことで、イメージに近づけていくことができます。
【最重要】動画生成AIと著作権:安心して使うための法的知識
動画生成AIの利用で最も注意すべき点が「著作権」です。知らずに他者の権利を侵害してしまうと、法的なトラブルに発展する可能性があります。ここでは、安心して創作活動を行うために知っておくべきポイントを解説します。
AIが作った動画、著作権は誰のもの?【文化庁の見解】
日本の文化庁の見解では、AIが完全に自律的に生成したコンテンツには、人間の「思想又は感情の創作的表現」が含まれないため、原則として著作権は発生しないとされています。これは、AI生成物がパブリックドメイン(公有)になる可能性があることを意味します。
しかし、人間がプロンプトを工夫したり、生成された動画に編集を加えたりして**「創作的な寄与」**が認められる場合は、その人間が著作者となり、著作権が発生する可能性があります。
知らないと危険!著作権侵害になる2つの条件
AI生成物が他者の著作権を侵害するかどうかは、通常の著作物と同様に、以下の2つの要件で判断されます。
- 類似性: 生成物が、既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」と似ていること。
- 依拠性: 生成する際に、既存の著作物を参考に(依拠して)いること。
たとえ偶然似てしまっただけであっても、AIが学習データとしてその著作物を利用していた場合、「依拠性」が認められて著作権侵害と判断されるリスクがあります。
AIの学習データに潜む著作権侵害のリスク
多くの動画生成AIは、インターネット上から収集した膨大なデータを学習しています。この中には、著作権で保護された動画や画像が無許諾で含まれている可能性があり、これが紛争の火種となっています。
実際に、ニューヨーク・タイムズ紙や多くのアーティストが、自社のコンテンツが無断でAIの学習に使用されたとして、OpenAIなどのAI開発企業を相手に訴訟を起こしています。また、中国では、AIが「ウルトラマン」の画像を無断で学習・生成したとして、開発事業者に賠償命令が下された判例もあります。
著作権トラブルを回避!ユーザーが今すぐできる4つの対策
では、利用者はどのようにリスクを回避すればよいのでしょうか。
商用利用可能なツールを選ぶ
各ツールの利用規約を必ず確認し、「商用利用可能」と明記されているプランを選びましょう。Runwayのように全プランで商用利用を認めているものもあれば、Pikaのように最上位プラン限定の場合もあります。
著作権フリーのデータで学習したAIを選ぶ
Adobeの「Firefly」のように、学習データが著作権的にクリーンであることを保証しているサービスを選ぶと、より安心して利用できます。
生成物をチェックする
生成した動画が、特定のキャラクターやブランドロゴ、既存の作品に酷似していないか、公開前に必ず確認しましょう。
具体的な指示でオリジナリティを出す
プロンプトを工夫し、AIに創作の大部分を委ねるのではなく、あくまで「道具」として利用することで、自身の創作的寄与を高め、著作権侵害のリスクを低減できます。
まとめ
動画生成AIは、私たちの創造性を解き放つ強力なツールです。その一方で、著作権をはじめとする法的なリスクも伴います。本ガイドで紹介した各ツールの特徴や料金プラン、利用規約を正しく理解し、特に著作権への意識を高く持つことが、この新しい技術と賢く付き合っていくための鍵となります。あなたも安全でクリエイティブな動画制作の世界に飛び込んでみませんか。