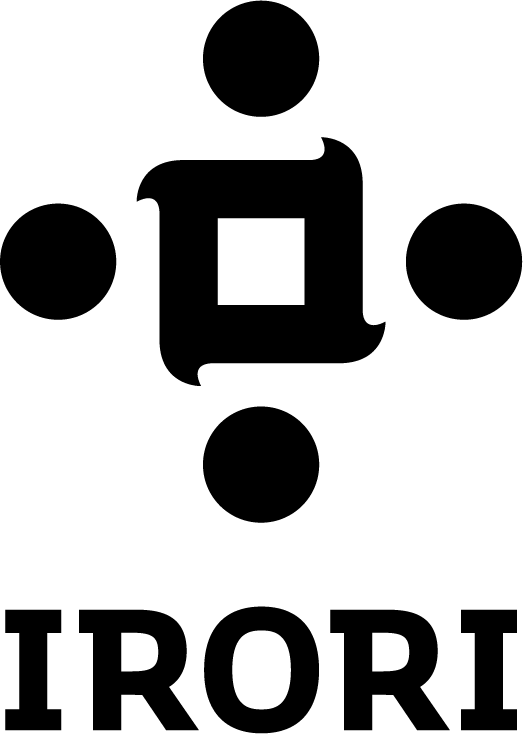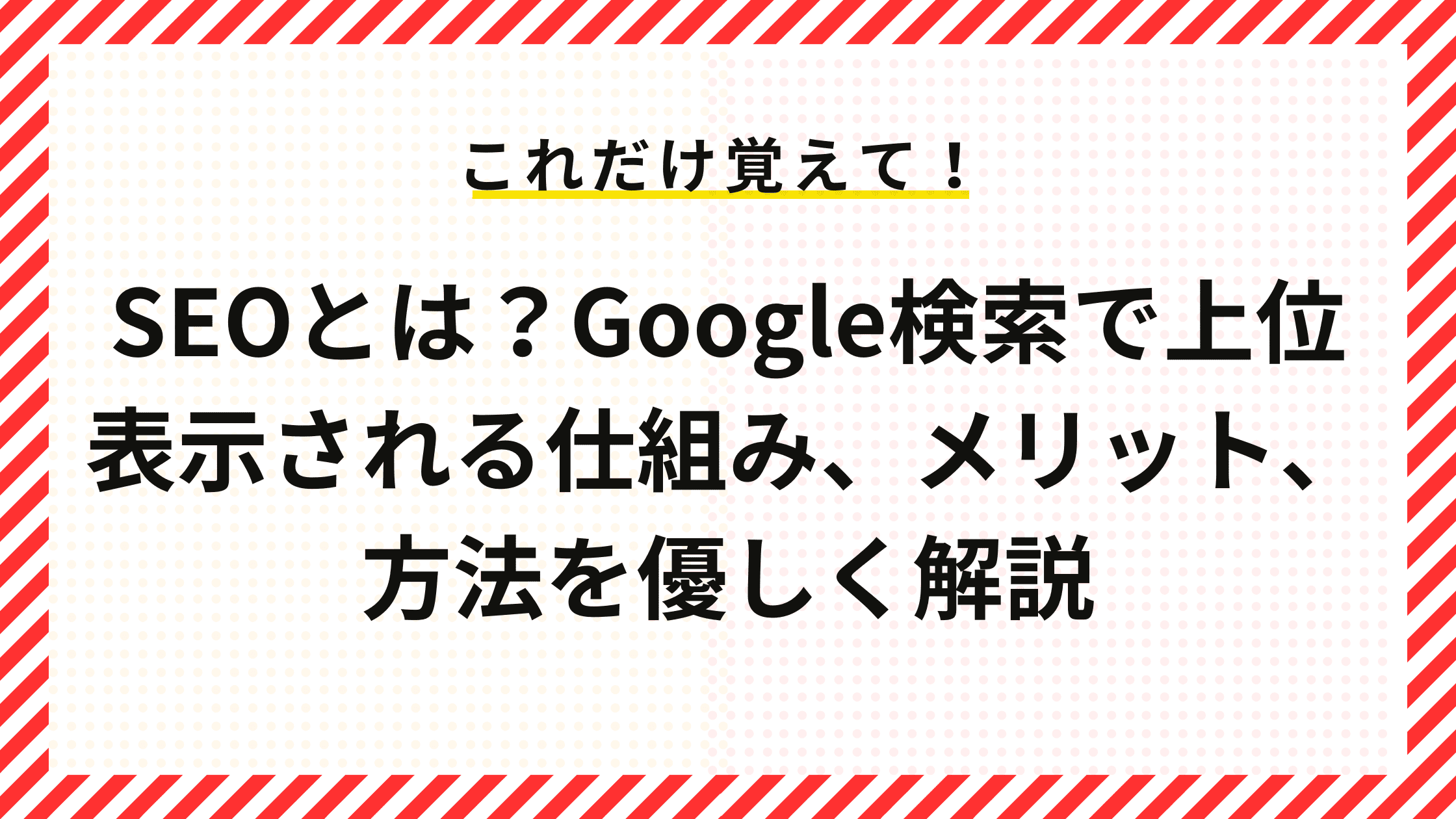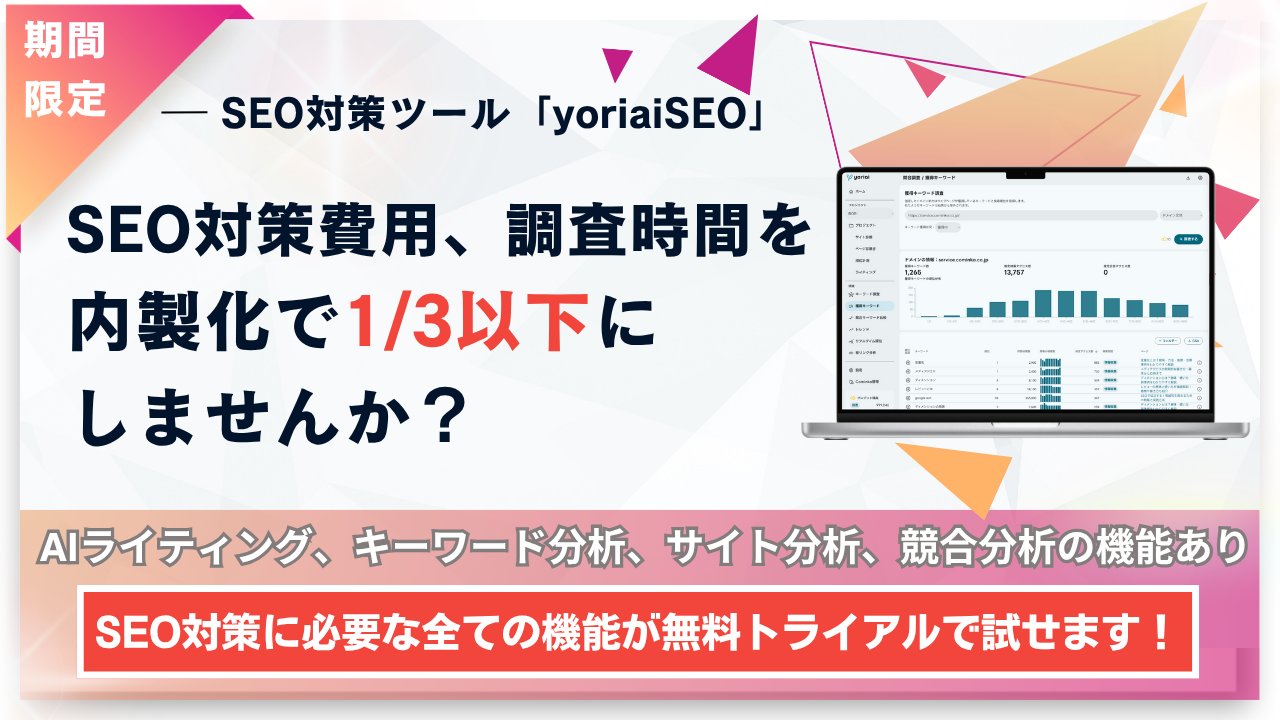自分のサイトをもっと多くの人に見てもらいたい。 Webサイトを運営している方なら、誰もがそう思うはずです。そこで必ず耳にするのがSEO(エスイーオー)という言葉。
難しそう、専門知識がないと無理と思われがちですが、本質はとてもシンプルです。この記事では、SEOの基本から、Googleがどのような基準でページを評価しているのか、初心者の方に向けてわかりやすく解説します。
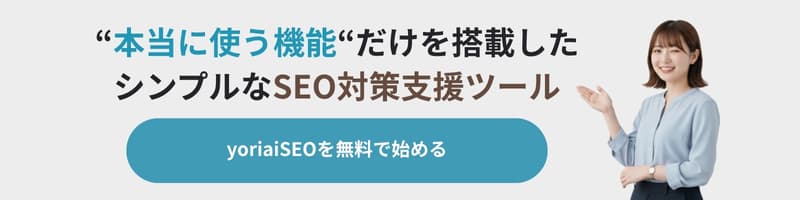
SEOの正体はユーザーへの最高のおもてなし
SEOはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略ですが、この言葉を覚える必要はありません。
一昔前は裏技を使ってGoogleを騙し、順位を上げるテクニックが流行ったこともありました。しかし、2025年の今、そのような小手先の技術は通用しません。
現在の正しいSEOの定義は、以下のようになります。
検索する人が困っていること(悩み)に対して、最高の答え(コンテンツ)を用意し、Googleと読者の両方から信頼されること。
つまり、Googleのロボットを攻略するのではなく、画面の向こうにいるユーザーに満足してもらうことが、結果として検索順位アップにつながるのです。Googleも、ユーザーを第一に考えれば、結果はあとからついてくると公言しています。
なぜ広告ではなくSEOなのか?
Webサイトにお客さんを集める方法は、大きく分けて広告とSEOの2つがあります。SEOをおすすめする最大の理由は、書いた記事があなたの資産になるからです。
Web広告(リスティング広告など) お金を払っている間だけ表示されます。家賃を払ってお店を出しているようなもので、支払いを止めると集客もゼロになります。
SEO(検索順位アップ) 一度上位に表示されれば、広告費を払わなくても24時間365日、自動でお客さんを集めてくれます。これは、自分の土地に家(資産)を建てることに似ています。
時間はかかりますが、コツコツと積み上げたコンテンツは、長くあなたのビジネスを支える強力な味方になってくれます。
Googleはどうやって順位を決めているの?
SEOを行うには、GoogleがどうやってWebページを見つけ、順位をつけているのかを知る必要があります。これは図書館の仕組みに例えると非常にわかりやすくなります。
検索エンジンの仕組みは、大きく発見(クロール)、登録(インデックス)、順位決定(ランキング)の3つのステップで動いています。
ステップ1:発見(クロール)
Googleにはクローラーと呼ばれるロボットがいます。このロボットは世界中のWebサイトを巡回し、新しいページや更新されたページがないかを探しています。図書館の司書さんが、新しい本を回収して回っているイメージです。
ロボットはリンクを辿って移動します。他のページからリンクがつながっていない孤立したページは、ロボットが見つけることができません。
ステップ2:登録(インデックス)
ロボットが集めてきたデータは、Googleの巨大なデータベースに登録されます。これをインデックスと呼びます。図書館で言えば、回収した本の内容を確認し、これは料理の本、これは歴史の本と分類して棚に並べる作業です。
インデックス(登録)されないと、検索結果には絶対に表示されません。ページを作ったのに検索に出てこないという悩みの大半は、この登録がうまくいっていないことが原因です。
ステップ3:順位決定(ランキング)
ここが最も重要です。ユーザーが検索窓にキーワードを入れた瞬間、Googleはインデックスされた膨大なページの中から、最もユーザーの役に立つページを選んで順位をつけます。
では、Googleは何を基準に良いページと判断しているのでしょうか。そこで重要になるのがE-E-A-Tという評価基準です。
今のSEOで最も重要な評価基準「E-E-A-T」
Googleは、検索品質評価ガイドラインの中でE-E-A-T(イーイーエーティー)という概念を非常に重視しています。これは、品質の高いコンテンツを見極めるための4つの基準です。
Experience(経験)
そのトピックについて、実体験を持っているかどうかが問われます。 AIやコタツ記事(ネットの情報だけで書いた記事)には出せない、人間ならではの価値です。 例:実際にその製品を使ってみた写真や感想、現地に行った際のエピソードなど。
Expertise(専門性)
その分野の知識やスキルを持っているかどうかが問われます。 広く浅い情報よりも、特定のテーマに特化したサイトの方が評価されやすくなります。 例:病気については医師、法律については弁護士など、専門家が書いているか。
Authoritativeness(権威性)
その分野で、誰が言っているかが重視されます。 社会的に認知されているか、他の信頼できるサイトから紹介(リンク)されているかなどが判断材料になります。 例:「〇〇のことならこのサイトだよね」と業界内で認められている状態。
Trustworthiness(信頼性)
運営者が誰か明確か、サイトは安全かという点です。 ユーザーが安心して利用できるサイトであることが大前提です。 例:運営者情報の開示、お問い合わせ先の明記、通信の暗号化(https)など。
これからのSEO記事作成では、単にキーワードを入れるだけでなく、自分自身の経験を語り、専門性を高め、信頼されるサイト作りを意識することが不可欠です。
検索キーワードの選び方とユーザー心理
記事を書く前に必ず行うのがキーワード選定です。しかし、ただ人気の言葉を選べば良いわけではありません。その言葉で検索する人が何を求めているのか、検索意図(インテント)を考えることが最重要です。
検索キーワードは、ユーザーの心理によって大きく4つに分類できます。
1. 知りたい(Knowクエリ)
悩みや疑問を解決したい状態です。 キーワード例:「SEOとは」「カレー 作り方」「iPhone 再起動できない」 対策:用語解説やハウツー記事などで、わかりやすく教えてあげることが必要です。
2. やりたい(Doクエリ)
何か行動を起こそうとしている状態です。 キーワード例:「メルマガ 登録」「アプリ ダウンロード」「美容院 予約」 対策:スムーズに申し込みやダウンロードができるページを用意します。
3. 行きたい(Goクエリ)
特定のサイトや場所に行きたい状態です。指名検索とも呼ばれます。 キーワード例:「Amazon」「YouTube」「〇〇株式会社」 対策:公式サイトが正しく表示されるように整えます。
4. 買いたい(Buyクエリ)
商品を購入したい、比較検討したいという、購買意欲が高い状態です。 キーワード例:「スニーカー 通販」「冷蔵庫 価格」「格安スマホ おすすめ」 対策:商品の魅力や価格比較、口コミ情報などを提供します。
ユーザーが今どの心理状態にあるのかを想像し、その目的にバッチリ合った記事を書くことが、SEO成功への第一歩です。
検索キーワードの選び方とユーザーの心を読み解くツール
どんな言葉で記事を書けばいいのか迷ったとき、自分の想像だけでキーワードを決めてはいけません。Googleが提供している無料のヒントを活用しましょう。
サジェスト機能はユーザーのニーズそのもの
検索窓にキーワードを入れると、自動的に候補が表示されますよね?あれをサジェスト(オートコンプリート)と呼びます。 これは、Googleが「みんなこんな言葉も一緒に検索していますよ」と教えてくれているリストです。つまり、そこに表示される言葉こそが、多くの人が実際に知りたがっている悩みや質問なのです。
例えば「SEO」と入力して、「SEO 初心者」と出てきたら、初心者向けの記事が求められています。「SEO 費用」と出てきたら、料金相場を知りたい人が多いということです。このサジェストに出てくる言葉をテーマに記事を書くのが、失敗しないキーワード選びのコツです。
読まれる記事の書き方と「良いコンテンツ」の条件
キーワードが決まったら、次は記事の作成です。Googleに評価され、ユーザーにも最後まで読まれる記事には共通点があります。
タイトルは看板!30文字で心を掴む
検索結果に表示されるタイトルは、お店の看板と同じです。中身が良くても、看板が魅力的でなければクリックされません。 検索されたキーワードを必ず含めること。 文字数は30文字程度(スマホで表示される限界)に収めること。 クリックしたくなるメリット(「5分でわかる」「プロが教える」など)を入れること。 この3つを意識するだけで、アクセス数は大きく変わります。
AI(ChatGPTなど)で記事を書いてもいいの?
最近増えている質問ですが、Googleの公式見解は「制作方法(人間かAIか)よりも、コンテンツの質を重視する」です。つまり、AIを使っても問題はありません。
ただし、AIが書いた文章をそのままコピペするのは危険です。なぜなら、AIはネット上の既存情報をまとめるのは得意ですが、そこに新しい体験や独自の視点がないからです。 AIはあくまでアシスタントとして使い、構成案を出してもらったり、文章のたたき台を作ってもらったりするのに留めましょう。そこに必ず、あなた自身の体験談(Experience)や感想を書き加えることで、Googleが評価するオリジナルな記事になります。
サイトの裏側を整える技術(内部施策)
良い記事を書いても、土台となるサイトの構造が整っていなければ、Googleは正しく評価してくれません。これを内部施策と呼びます。家づくりで言えば、基礎工事や骨組みにあたる部分です。
見出しタグ(h1, h2, h3)を正しく使う
記事を書くとき、文字のサイズだけで見出しを作っていませんか?HTMLのルールに従って、見出しタグを使うことが重要です。
h1:記事のタイトル(1ページに1回だけ) h2:大見出し(章) h3:小見出し(節)
このように順序よく使うことで、Googleのロボットに「ここが重要なテーマだな」と伝えることができます。
スマホでの見やすさと表示速度
今や検索の主役はスマートフォンです。Googleもスマホサイトの内容を基準に評価を行っています(モバイルファーストインデックス)。 文字が小さすぎないか、ボタンが押しにくくないかを確認しましょう。また、ページの表示速度も重要です。画像サイズを小さくするなどして、サクサク動くサイトを目指してください。表示に3秒以上かかると、多くのユーザーは待てずに帰ってしまいます。
これだけは絶対にダメ!SEOのNG行為
最後に、SEOで絶対にやってはいけない禁止事項をお伝えします。これらを行うと、検索順位が下がるどころか、検索結果から削除されるペナルティを受ける可能性があります。
リンクをお金で買う
他のサイトからリンクを貼ってもらうことはSEOに効果的ですが、業者にお金を払ってリンクを買う行為は厳禁です。Googleはこれを厳しく監視しており、見つかると大きなペナルティを受けます。
コピーコンテンツ(パクリ)
他人のサイトの文章をコピーして自分の記事として公開することです。著作権の問題はもちろん、Googleはオリジナルではない情報を評価しません。
隠しテキスト
背景と同じ色の文字でキーワードを埋め込み、ユーザーには見えないけれどロボットには読ませようとする古い手口です。これも現在は完全にスパム(不正行為)扱いされます。
まとめ:SEOはユーザーへの思いやり
SEOの技術は日々進化していますが、本質はずっと変わりません。 それは、検索してくれたユーザーの「知りたい」「解決したい」という気持ちに、誠実に答えることです。
小手先のテクニックに走るのではなく、どうすればもっと分かりやすくなるか、どうすればもっと役に立つかを考え続けること。その積み重ねが、結果としてGoogleからの評価、そしてユーザーからの信頼につながります。
まずは、あなたが一番書きやすいテーマで、目の前の誰かの役に立つ記事を一本書いてみることから始めてみませんか?