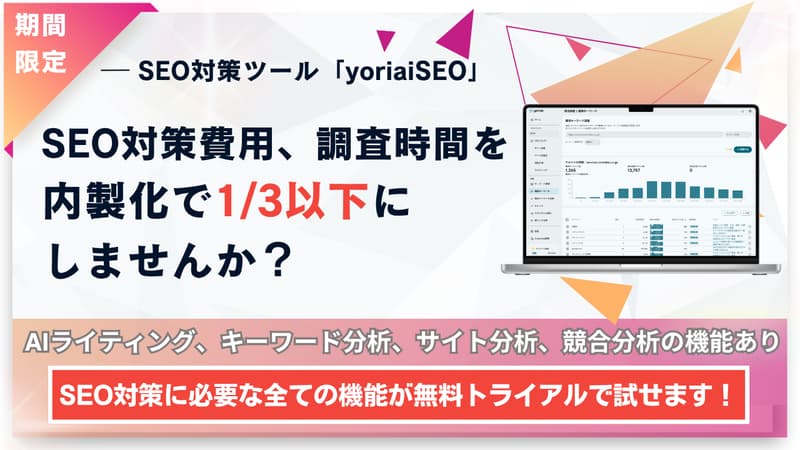はじめに:AI登場でウェブサイト運営はどう変わる?
最近、「AI」という言葉をよく耳にしますよね。特に、まるで人間のように文章を理解したり、質問に答えたりできる賢いAIが登場し、私たちの情報収集の方法やウェブサイトとの関わり方が大きく変わろうとしています。
LLM(大規模言語モデル)の普及と新たな課題
その賢いAIの代表格が「LLM(大規模言語モデル)」です。これは、インターネット上の膨大な文章などを学習して、人間のような自然な文章を作り出せるAIのこと。チャットで質問に答えてくれたり、文章を要約してくれたり、様々な場面で活躍し始めています。
ウェブサイトを運営している方にとっては、このLLMに自分たちのサイト情報を正しく理解してもらい、うまく活用してもらうことが、これからの時代に重要になってきます。しかし、何もしなければ、LLMがサイトの内容を誤解したり、大切な情報を見逃したりする可能性もあります。
llms.txtとは何か?この記事でわかること
そこで登場したのが「llms.txt」という新しいファイル形式の提案です。これは、ウェブサイト側からLLMに対して「私たちのサイトはこのように利用してくださいね」と伝えるための、いわばLLM向けの指示書のようなもの。
この記事では、
- llms.txtとは具体的に何なのか?
- AIの普及で、これまでのウェブサイト集客(SEO)はどう変わるのか?
- llms.txtは本当に効果があるのか?専門家や現場の声は?
- 結局、llms.txtを導入すべきなのか?
といった点を、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。llms.txtへの期待だけでなく、現実的な課題も踏まえて、AI時代のウェブサイト運営について一緒に考えていきましょう。
llms.txtの基本:LLMとの関係を理解しよう
まずは、llms.txtがどのようなものか、基本から見ていきましょう。
llms.txtの役割:LLMへの「指示書」
llms.txtの主な役割は、ウェブサイトの運営者が、LLM(大規模言語モデル)という賢いAIに対して、「このサイトの情報は、このように扱ってください」と伝えることです。例えば、「このページの情報は学習に使っていいですよ」「この部分は引用しないでくださいね」といったルールを示すことを目的として提案されました。
LLM(大規模言語モデル)って何?
ここで改めて、LLMについて簡単におさらいしましょう。
- LLM(大規模言語モデル)とは: たくさんの文章を読んで学習し、人間が使う言葉(自然言語)を理解したり、生成したりするのが得意なAIの一種です。ChatGPTやGoogleのGeminiなどが有名ですね。
LLMの仕組み(かんたんに)
LLMは、たくさんの文章データから「この単語の後にはこの単語が来やすい」といった言葉の繋がりやパターンを学習します。これにより、質問に対して自然な文章で答えたり、新しい文章を作り出したりすることができます。
LLMの種類
LLMには様々な種類があり、開発している企業や、得意なこと(文章作成、翻訳、会話など)が異なります。
LLMが学習するもの
主にインターネット上のウェブサイトや書籍、ニュース記事など、膨大な量のテキストデータを学習しています。だからこそ、幅広い知識を持っているのです。
比較:robots.txtとの違い
ウェブサイト運営に詳しい方なら「robots.txt」というファイルを聞いたことがあるかもしれません。llms.txtと似ているようで、役割が異なります。
robots.txtとは?(ウェブサイトの交通整理役)
- robots.txtとは: Googleなどの検索エンジンがウェブサイトの情報収集に来る「ウェブクローラー(ボット)」というプログラムに対して、「このページは見てもいいけど、このページは見ないでください」と伝えるためのファイルです。ウェブサイトの交通整理役のようなイメージですね。主にアクセス制御のために使われます。
llms.txtとの役割分担(期待される役割)
llms.txtは、robots.txtよりもさらに踏み込んで、LLMに対して「情報をどのように利用してほしいか(またはほしくないか)」という、より詳細な指示を出すことを目指しています。アクセス制御だけでなく、利用方法のルールまで伝えようとする点が異なります。(ただし、これはあくまで提案段階の考え方です。)
AI普及とSEOの変化:これまでの常識は通用しない?
LLMのようなAIが登場したことで、人々が情報を探す方法が変わり、ウェブサイトの集客方法、いわゆる「SEO(検索エンジン最適化)」にも大きな影響が出てきています。
- SEO(検索エンジン最適化)とは: Search Engine Optimizationの略。Googleなどの検索エンジンで、自分のウェブサイトが検索結果の上位に表示されるように、ウェブサイトの内容や構造を工夫することです。
検索の仕方が変わる:AIによる回答生成
これまでは、何か知りたいことがあると検索エンジンで検索し、表示されたウェブサイトのリンクをクリックして情報を見つけるのが一般的でした。しかし、これからはAIが直接答えを生成してくれる場面が増えるかもしれません。
SGE(Search Generative Experience)とは?(Googleの新しい検索体験)
- SGE(Search Generative Experience)とは: Googleが開発中の新しい検索の形。検索結果の一番上に、AIが生成した答えの要約などが表示されるようになります。(※2025年4月時点、まだ一部地域でのテスト段階です)
ゼロクリックサーチとは?(サイトを見ずに答えがわかる)
SGEのような機能が普及すると、ユーザーは検索結果画面でAIが生成した答えを見るだけで満足し、わざわざウェブサイトをクリックしなくなるかもしれません。これを「ゼロクリックサーチ」と呼びます。ウェブサイトへのアクセス数が減ってしまう可能性があるのです。
SEO(検索エンジン最適化)への影響
こうした変化は、従来のSEOの手法にも見直しを迫ります。
キーワードだけじゃない:「検索意図(インテント)」に応える重要性
これまでは特定のキーワードで上位表示を目指すことが重視されましたが、今後はユーザーが「なぜそのキーワードで検索したのか?(検索意図=インテント)」を深く理解し、その疑問や悩みに的確に、そして分かりやすく答えるコンテンツを作ることがより重要になります。
コンテンツの質と信頼性:「E-E-A-T」がより重要に
AIが簡単に文章を作れる時代だからこそ、情報の「質」と「信頼性」がこれまで以上に問われます。Googleはウェブサイトの品質を評価する基準として「E-E-A-T」を重視しています。
- E-E-A-Tとは: Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字。情報の書き手が、その分野で実際に経験を持ち、専門知識があり、その道の権威として認められていて、情報全体が信頼できるか、という基準です。
誰が書いた情報なのか、どんな根拠に基づいているのかを明確にすることが、AIが生成した情報との差別化に繋がります。
被リンク(外部リンク)の価値の変化
他のサイトから自分のサイトへリンクが貼られること(被リンク)は、SEOにおいて重要な要素ですが、その質がより問われるようになるでしょう。単に数が多いだけでなく、関連性の高い、信頼できるサイトからのリンクが評価される傾向が強まると考えられます。
LLMO(大規模言語モデル最適化)の必要性
これからのウェブサイト運営では、従来の検索エンジン対策(SEO)だけでなく、LLMにいかに自サイトの情報を正しく、好意的に扱ってもらうか、という新しい視点が必要になります。これを「LLMO(大規模言語モデル最適化)」と呼ぶことがあります。
- LLMO(大規模言語モデル最適化)とは: Large Language Model Optimizationの略。LLM(大規模言語モデル)が、自社のウェブサイトの情報を学習したり、参照したりする際に、より正確に、そして望ましい形で扱ってくれるようにウェブサイトを最適化することを目指す考え方です。
llms.txtは、このLLMOを実現するための手段の一つとして期待されていました。
llms.txtへの期待と現実:本当に効果はあるの?
llms.txtは、LLMとの新しい関係を築くためのツールとして期待されて登場しました。しかし、その効果については、様々な意見が出ています。
期待されていた役割
llms.txtが提案された当初、以下のような役割が期待されていました。
- LLMへの「道しるべ」: サイトの構造や重要なページをLLMに伝え、理解を助ける。
- E-E-A-Tの伝達補助: 運営者情報など、サイトの信頼性を示す情報へのリンクを伝え、LLMの評価を助ける。
- コンテンツ利用の制御と促進: LLMに学習してほしい/ほしくないコンテンツを指定したり、API連携(※後述)を促したりする。
- 間接的なSEO効果: LLMがサイトを正しく評価することで、AI検索での引用が増え、間接的に検索順位にも良い影響を与える。
現実:専門家からの懐疑的な声
しかし、これらの期待に対して、Googleの専門家などからは懐疑的な声が上がっています。
Google ジョン・ミュラー氏の見解
Googleのサーチ・アドボケイト(検索技術の広報担当のような役割)であるジョン・ミュラー氏は、llms.txtについて以下のような厳しい見解を示しています。
- 「主要AIサービスは利用していない」
- 「私の知る限り、どのAIサービスもLLMs.TXTを使用しているとは言っていません」と述べ、実際にLLMがllms.txtを読み込んでいる形跡がないことを指摘しています。ウェブサイトのアクセス記録(サーバーログ)を見ても、LLMがllms.txtを確認しに来ている様子はない、という報告もあります。
- 「キーワードメタタグと同じ?」
- llms.txtは、サイト運営者が「私のサイトはこういう内容です」と一方的に主張するものに過ぎず、その信頼性は低いと考えています。これは、かつてSEOで使われたものの、今は検索エンジンがほとんど参考にしない「キーワードメタタグ」に似ている、という指摘です。
- キーワードメタタグとは: 昔、ウェブページの内容を示すキーワードを記述するために使われたHTMLタグ。しかし、無関係なキーワードを詰め込むなどの悪用が横行したため、現在の主要な検索エンジンはほとんど評価の対象としていません。
- llms.txtは、サイト運営者が「私のサイトはこういう内容です」と一方的に主張するものに過ぎず、その信頼性は低いと考えています。これは、かつてSEOで使われたものの、今は検索エンジンがほとんど参考にしない「キーワードメタタグ」に似ている、という指摘です。
- 「ウェブサイトを見れば十分では?」
- LLMは元々ウェブサイト全体の情報を読み込んで理解する能力があるため、わざわざllms.txtという別のファイルを用意する必要があるのか?と疑問を呈しています。
- 「悪用(クローキング)のリスク」
- llms.txtにはLLM向けの良い情報を書きつつ、実際のウェブサイトにはユーザーや検索エンジン向けに別の(質の低い)内容を見せる、といった不正行為(クローキング)に使われる危険性を指摘しています。
- クローキングとは: ウェブサイトにアクセスしてきた相手(人間か、検索エンジンのクローラーかなど)によって、見せるページの内容を変える不正な手法のこと。検索エンジンを騙す行為としてペナルティの対象となります。
- llms.txtにはLLM向けの良い情報を書きつつ、実際のウェブサイトにはユーザーや検索エンジン向けに別の(質の低い)内容を見せる、といった不正行為(クローキング)に使われる危険性を指摘しています。
参照記事:Google Says LLMs.Txt Comparable To Keywords Meta Tag
現場の声:アクセスログでの反応は?
ジョン・ミュラー氏の指摘を裏付けるように、実際にllms.txtを設置したウェブマスター(ウェブサイト管理者)たちからも、「サーバーログを見ても、有名なAIからのアクセスはほとんどない」「設置してみたけれど、特に何も変化がない」といった声が多く聞かれます。
cominkaの見解:導入してみた結果
私たちcominkaでも、自社で運営する情報サイト(オウンドメディア)「IRORI」で、試験的にllms.txtを導入してみました。
オウンドメディア「IRORI」での状況
導入後、ウェブサイトのアクセス状況や検索順位などを継続的に観察しましたが、現時点(2025年4月)で、llms.txtを設置したことによる目立った順位変動や、LLMからのアクセス増加といった明確な効果は確認できていません。
現時点での効果と優先度
これらの状況から、cominkaとしては、現段階でllms.txt対策に多くの時間や労力をかける必要はなく、その優先度は低いと考えています。他のもっと効果が実証されているSEO施策や、コンテンツの質を高める努力に時間をかけるべきでしょう。
llms.txtの作り方:基本ルールと設定項目(参考情報)
現時点では優先度が低いとはいえ、llms.txtがどのようなものか、作り方の基本(想定されているルール)を知っておくことは無駄ではありません。ただし、これはまだ正式に標準化されたものではない点に注意してください。
ファイルの置き場所と名前
- 場所: ウェブサイトの一番上の階層である「ルートディレクトリ」に置くことが想定されています。(例:
https://www.example.com/llms.txt) - ルートディレクトリとは: ウェブサイトの住所(URL)で、ドメイン名(例:
www.example.com)のすぐ後ろの部分。ウェブサイトのファイルの सबसे上位のフォルダのことです。 - ファイル名:
llms.txtというファイル名にします。
想定される記述ルール(注意:標準化されていません)
- シンプルなテキスト形式(
robots.txtに似た形式)や、Markdown形式(見出しなどが使えるメモ帳のような形式)が議論されていますが、決まった形式はありません。 - 基本的には、1行に1つの指示を書くような形が想定されています。
想定される設定項目例
以下は、llms.txtに書かれるかもしれない項目(指示)の例です。
User-Agent:
指示の対象となるAI(LLM)を指定します。* は「すべてのAI」を意味します。特定のAI(例: ChatGPT-User)を指定することも考えられます。
Allow: / Disallow:
AIにアクセスや学習を許可するページ(Allow:)や、拒否するページ(Disallow:)を指定します。robots.txtと考え方は似ています。
Usage Policy: (利用ルール)
「要約はOKだけど、長文の引用は控えてほしい」といった、コンテンツの利用に関する希望を伝える項目が将来的にできるかもしれません。(現在は標準ではありません)
API Endpoint: (外部連携の窓口)
もし、ウェブサイトの機能を外部のプログラム(LLMなど)から利用できる仕組み(API)があれば、その接続情報を示します。
APIとは: Application Programming Interfaceの略。異なるソフトウェアやプログラム同士が、お互いの機能や情報を利用するために定められた「会話のルール」や「窓口」のようなものです。
Sitemap: (サイトの地図)
ウェブサイト全体のページ構成を示す「サイトマップ」ファイルの場所を伝えます。
繰り返しますが、これらはあくまで想定される例であり、実際にLLMがこれらの指示に従う保証はありません。
llms.txt導入の判断:現時点でどう考えるべきか
ここまで見てきたように、llms.txtには期待された役割がある一方で、その効果には疑問の声が多く上がっています。では、現時点で導入をどのように考えるべきでしょうか?
メリット(期待されるもの)の再確認
もし将来的にLLMがllms.txtを参照するようになれば、以下のようなメリットが期待できるかもしれません。
- AI検索の結果で、自分のサイト情報が適切に引用されやすくなる。
- LLMがサイト情報を活用しやすくなり、新しいサービス連携などが生まれる可能性。
- LLMによる意図しない情報利用を防ぐ。
デメリットとリスク(現実的な課題)
しかし、現時点では以下のデメリットやリスクの方が大きいと言えます。
- 効果が不明: 主要なLLMが利用しておらず、導入しても効果が見込めない可能性が高い。
- 時間と労力の浪費: 効果が不明な対策にリソースを割くのは非効率的。
- 標準仕様がない: 正式なルールが決まっていないため、どのように書けば良いか不明確。
- 悪用のリスク: 将来的に参照されるようになった場合、不正な目的で利用される可能性がある。
導入の優先度:cominkaの推奨
これらの点を踏まえ、cominkaとしては以下の考え方を推奨します。
まずは基本のSEOとコンテンツ質向上を
llms.txtのような新しい技術に飛びつく前に、まずはウェブサイト運営の基本に立ち返りましょう。
- ユーザーにとって価値のある、質の高いコンテンツを作成・充実させること。
- E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を高めること。
- ウェブサイトの使いやすさ(ユーザーエクスペリエンス)を改善すること。
- 基本的なSEO対策(タイトル設定、見出し構造、内部リンクなど)を着実に実施すること。
- 構造化データを適切に実装すること。
- 構造化データとは: ウェブページの内容(例えば、レシピの材料や手順、イベントの日時や場所など)が何であるかを、検索エンジンなどのプログラムにも理解しやすいように、特定の書き方(スキーマ)で記述した情報のこと。ページの裏側に貼る「説明書きメモ」のようなものです。
これらの基本的な施策の方が、現時点でははるかに重要で効果的です。
リソースに余裕があれば…
もし、上記の基本的な施策を十分に行った上で、さらに時間や人員に余裕がある場合に限り、llms.txtの動向を注視し、基本的な設定だけを行っておく、という選択肢は考えられます。しかし、決して優先度の高い作業ではありません。
llms.txtの管理と今後の展望
もしllms.txtを設置する場合、または将来的に設置することになった場合に備えて、管理方法と今後の見通しについても触れておきます。
llms.txtファイルの管理方法
- バージョン管理のすすめ: ファイルの内容を変更したら、いつ、誰が、なぜ変更したのか記録を残せるように、Gitなどのバージョン管理ツールを使うと便利です。
- チーム内での情報共有: なぜ特定の指示を書いたのか、チーム内で目的や理由を共有しておくことが大切です。
llms.txtの未来はどうなる?
llms.txtが今後どうなっていくかは、まだ誰にも分かりません。
- 標準化は進むのか?
- ウェブ技術のルール作りを行う標準化団体(W3Cなど)や、関連企業が集まるコンソーシアムなどで、正式な仕様が議論され、標準化される可能性はあります。しかし、現状ではその動きは活発ではありません。
- 標準化団体(W3C)とは: World Wide Web Consortiumの略。ウェブで使われる技術(HTMLやCSSなど)の標準的なルールを決めている国際的な組織です。
- ウェブ技術のルール作りを行う標準化団体(W3Cなど)や、関連企業が集まるコンソーシアムなどで、正式な仕様が議論され、標準化される可能性はあります。しかし、現状ではその動きは活発ではありません。
- 機能は拡張される?
- もし標準化されるなら、単なるアクセス制御だけでなく、コンテンツのライセンス情報や、より詳細な利用ルールを指定できる機能などが追加されるかもしれません。AIが進化すれば、マルチモーダル(テキストだけでなく画像や音声も扱える)な指示が必要になる可能性もあります。
- 関連ツールは登場する?
- llms.txtの作成や管理を助けるツールが登場する可能性もあります。
cominkaのスタンス:将来への備えとして
AI技術の進歩は非常に速いため、今は役に立たないように見えるllms.txtも、将来重要な意味を持つ可能性は完全に否定できません。
そのため、cominkaとしては、「現時点では優先度は低いが、情報収集は続け、もしリソースに余裕があれば基本的な設定だけはしておく」というスタンスが良いのではないかと考えています。過度な期待はせず、しかし完全に無視もしない、というバランス感覚が大切です。
まとめ:llms.txtとAI時代のウェブサイト運営
今回は、AI時代に登場した新しいファイル「llms.txt」について、その役割への期待から、専門家による懐疑的な見方、そして現時点での現実的な評価までを詳しく解説しました。
llms.txtの現状評価(まとめ)
- 期待された役割: LLMへの指示書として、LLMの理解促進やコンテンツ利用制御が期待された。
- 現実: 主要なLLMは利用しておらず、設置しても目に見える効果はほとんどない。専門家からは有効性に疑問の声。
- 優先度: 現時点では、対策の優先度は低い。
- 将来性: 不透明だが、AIの進化次第では重要になる可能性もゼロではない。
今、ウェブサイト運営者が取るべき行動
llms.txtに多くの時間を使うよりも、まずは以下のことに注力しましょう。
- ユーザー第一の高品質なコンテンツ作成: 読者の疑問や悩みに真摯に答え、信頼できる情報を提供する。
- 基本的なSEO対策の徹底: サイト構造、表示速度、モバイル対応などを最適化する。
- E-E-A-Tの向上: 誰が、どのような根拠で情報を発信しているかを明確にする。
- llms.txtの動向は情報収集程度に: 最新情報はチェックしつつ、リソースに余裕があれば基本的な設定を検討する。
AI時代も変わらない大切なこと
技術は常に変化しますが、ウェブサイト運営の本質は変わりません。それは、「訪問してくれるユーザーにとって、本当に価値のある情報や体験を提供すること」です。この基本を忘れずに、AIという新しい技術と上手に付き合っていくことが、これからのウェブサイト運営には求められるでしょう。
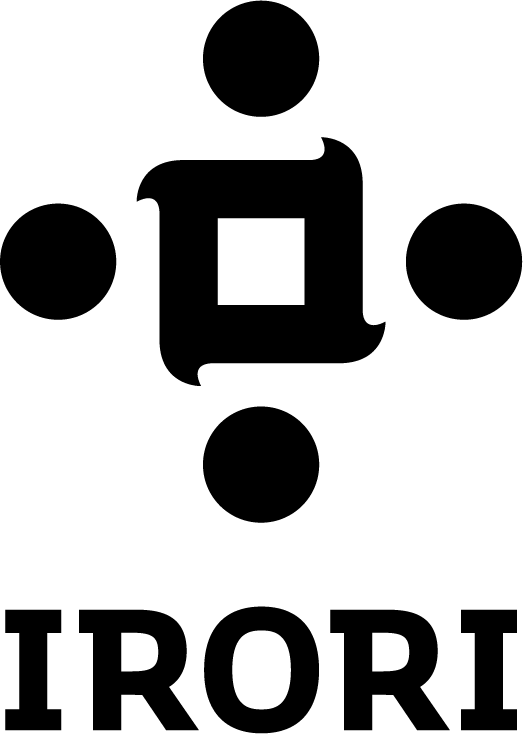

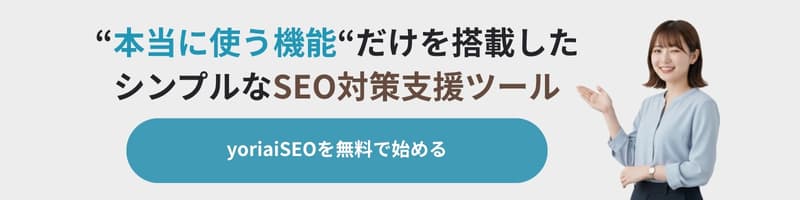

A-Iとは?AIツールの比較や活用方法を解説.png)